| メイン |
Job Description 16: 熟練剣士 【アラトリステ】
2009年1月21日 就職・転職 コメント (6)
17世紀前半、スペインは隣国ポルトガルを併合し、アルマダの海戦に敗れつつもいまだ世界の覇権を掌中に収めていました。しかしフランドルでのオランダとの戦争はいつまでも絶えることがなく(八十年戦争)、やがて西仏戦争が勃発、カタルーニャやポルトガルでは大規模な反乱も起きるなど、その繁栄には少しずつ翳りが差し始めます。スペイン映画“アラトリステ”では、こうした時代のイベリア半島を駆け抜けた一人の剣士の生涯が描かれました。
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
| メイン |


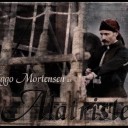

コメント
アラトリステはそうですね、DVDよりできれば映画館で、というタイプの作品でした。
よろしくお願いします~
記録し始めると夢の内容にも影響あることって個人的にはあると思うんですが、どうですかね。今後とも更新楽しみにしています~
夢自体に大それた意味はないと思いますw
というのもわたしは確実にその種の人間の一人で、うたたねのなかで見る夢がけっこう日常的な疑問解決の糸口になったりもします。それに空飛ぶ夢とか、単純に楽しいですしねw