18世紀前半、パリの最貧区に超人的な嗅覚をもった男の子が生まれ落ちます。その天性の才能はやがて、青年期のある夜に意図せず殺してしまった少女の香りによって昇華され、そこから彼の人生は‘許されざる’疾走を始めてゆきます。
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
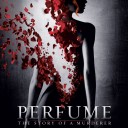



コメント