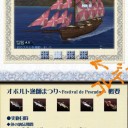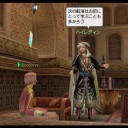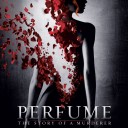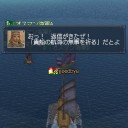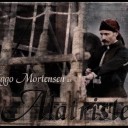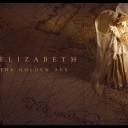有楽町のビックカメラが入る読売会館を北に回り、東京国際フォーラムの建つブロックへと歩く。ビルの谷間風が頬に当たる。遠くから見た有楽町駅改札の様子からは、どうも駅構内から乗客を退避させたらしい。ビックカメラも入り口から覗く店内は大型液晶やら携帯の仰々しい販売ブースやらで普段通りにまぶしいほどだが、道にはひとが溢れているのに出入りする客がいない。やはりいったん店を閉じたようだ。そういえばここまで歩く途上でも、建物から客を追い出している店を散見した。丸の内の高層ビル群の1,2階に入る高級雑貨店やブランドショップはどれも、全面ガラス張りの窓から通りへと目一杯に自店舗の魅力を訴えているが、贅沢で洒落たその内装が客を失ったことで何か主役不在のドールハウスのような奇妙さを醸し出していた。
しかしそうしてひとを店内から吐き出す処置は、果たして本当に良いことなのか。軽い違和感が走る。たしかに何が起きるかわからない状況で、店側が人的被害の責任を最小限に抑えるためには店内の客数をゼロにするのがベストだろう。だが多くの店がそのように最善の自衛策を個別に選んだ結果として、ビル群の谷間にひとがうごめいているこの状況はどうか。さらに激しい揺れが起きたとき、最初に大崩落を起こすとすればビル壁面に張られた大量の窓ガラスだろう。それを通りの人々が全身で浴びることになる。そうなればガラスの破片による切り傷や擦り傷だけで済む者、頭蓋骨を陥没させられて即死する者はむしろ幸運だ。周囲はきっと血の海になる。頸動脈を切られ、内蔵をえぐり出され、あるいは手足をもがれる者が続出し、一帯は阿鼻叫喚の地獄と化すだろう。ましてやJRだ。JRの鉄骨とコンクリートで守られた駅構内が、ビルの谷間の狭い車道によりも危険だとは到底思えない。それに構内から吐き出された、必ずしも土地勘があるとは限らない人々が付近の避難区域へと即座に集合できるはずもない。ひとを吐き出すなら吐き出すで、避難指定区域への誘導とセットでなければ巨視的には意味がない。
東京国際フォーラムの地上広場へ着く。ホール棟とガラス棟の間にあるこの広場にもやはり、ひとは入り乱れていた。“ガラスの船”として知られるガラス棟の正面入り口には、ガードマンやイヤホンをつけた職員が4、5名立ち並び、両腕を後ろに組み胸を反らせた姿勢で群衆の建物内への侵入を阻んでいる。衛兵然としたその威圧感に少し驚く。「お客さまの安全のため」という言葉の裏に本来はひそむべき“無用の責任は勘弁”という組織の本音が丸出し過ぎて、前衛コントのようなシュールさを感じた。なにしろ余震はまだ散発的に続いていて、“ガラスの船”の舷側のそと数十センチのエリアには、行き場を失った人々が群れているのだ。その真上に数十メートルのガラスの壁がそびえ建っている。主に会議室の多く入るガラス棟と広場に対面して建つホール棟群は地上階よりも2階3階のほうが広い構造だし、これで崩落規模の震動が来たらいったいここにいる何割が助かるだろう。しかしそうした想像が働くのは自分が目前の事態に何の責務も負っていないからで、何らかの職責を負ってこの場に遭遇した人々、つまり職員や駅員たちにとって重要なのは、仮にどれだけ違和感を覚えていたとしてもたぶん職責のほうなのだろう。だが結果として、その一見責務に篤い行動が客観的には単なる思考停止としか映らない、ということもまた十分あり得る話だ。ふとかつての福知山線脱線事故を思い起こす。あれなどまさに組織が要請する個々の職業意識の連鎖が、まだ若い一運転士の内面へと吹き溜まった挙句の速度超過ではなかったか。
広場のなかほどへと進み、土踏まずのあたりに疲れを感じたので近場にあったベンチへと腰をおろす。しばらく何するでもなくあたりを見回していると、屋外へ避難してたむろしているだけに見えていたビックカメラの店員たちの集団が、実はきちんと整列していたのに気がついた。10人ひと組の列が、よく見れば奥のほうまで20列近く並んで長方形の塊をつくっている。なんだろうとしばらく眺めていると、その集団のかたわらに大きなプラスチックケースが積まれていた。なかにはミネラルウォーターのペットボトルやスナック菓子、薬品類とおぼしきボックスや毛布などが入っている。ケースが積まれているといっても、それだけでは恐らく社員たちの分にしかならない。だが彼らが妙に気合が入った様子なのはなぜだろう。もしかしたら物資はもっと大量にあって、行き場をなくしたあたりの一般市民に配りだす意図でもあるのだろうか。まあそんなわけ、ないか。けれど、そういうことがあってもいいなと考える。ストック&フローを徹底した薄利多売を旨とする大型店舗の慌ただしい倉庫の物陰で、何年に一度も来ない出番をひっそりと緊急支援物資のひと山が待ち続ける。企業は利益を追求する。国は国益を最優先に行動する。だがその場合の利益国益とは本来何か。緊急時には見かけ上逆転しているような素振りを見せる集団こそ実は、より深い信念において揺るぎのない姿勢を貫いているといえる場合もあるだろう。
再び歩き始める。フォーラムの区画を北へ抜け、再び丸の内へ。ほんの2時間前とはまるで様子が変わっている。バス停は、バスの車内も外も黒山の人だかり。丸の内南口のそばに長蛇の列ができていて何かと思ってたどってみたら、列は中央口をまたいで丸の内北口のタクシー乗り場まで伸びていた。だが当のタクシーは一台も来ていない。だだっ広いタクシープールには虚しく寒風が吹いているだけだ。電車では帰れない、電話も通じない、歩いて帰るなど無謀、ゆえにタクシーを待つ列に並ぶほか打つ手がない、という思考経路をたどっているのだろう。だがその結果としてどうみても無意味な100メートル超のこの列に並ぶ選択を採ってしまうのは、純然たる思考停止にも思える。まだ混んではいるが来ているバスに並んでともかく都心を離れるとか、数ブロック歩いて流れのタクシーに期待をつなげるほうがマシではないか。まあ、五十歩百歩か。そうかもしれない。
少しからだの冷えを感じ始めたこともあり、いったん新丸ビルに入ってからだを温めることにする。ビルに入るとガラスの壁で隔てられた一区画で、多くの人が立ち尽して一方を見上げている。近づいてみると、彼らは壁2.5mほどの高さに嵌められた大型液晶の画面を、身動きじろぎもせず呆然と見つめていた。画面を見上げ、みなが呆然としている理由が即座にわかる。
……これは……なに?
つづく、かもしれず。
しかしそうしてひとを店内から吐き出す処置は、果たして本当に良いことなのか。軽い違和感が走る。たしかに何が起きるかわからない状況で、店側が人的被害の責任を最小限に抑えるためには店内の客数をゼロにするのがベストだろう。だが多くの店がそのように最善の自衛策を個別に選んだ結果として、ビル群の谷間にひとがうごめいているこの状況はどうか。さらに激しい揺れが起きたとき、最初に大崩落を起こすとすればビル壁面に張られた大量の窓ガラスだろう。それを通りの人々が全身で浴びることになる。そうなればガラスの破片による切り傷や擦り傷だけで済む者、頭蓋骨を陥没させられて即死する者はむしろ幸運だ。周囲はきっと血の海になる。頸動脈を切られ、内蔵をえぐり出され、あるいは手足をもがれる者が続出し、一帯は阿鼻叫喚の地獄と化すだろう。ましてやJRだ。JRの鉄骨とコンクリートで守られた駅構内が、ビルの谷間の狭い車道によりも危険だとは到底思えない。それに構内から吐き出された、必ずしも土地勘があるとは限らない人々が付近の避難区域へと即座に集合できるはずもない。ひとを吐き出すなら吐き出すで、避難指定区域への誘導とセットでなければ巨視的には意味がない。
東京国際フォーラムの地上広場へ着く。ホール棟とガラス棟の間にあるこの広場にもやはり、ひとは入り乱れていた。“ガラスの船”として知られるガラス棟の正面入り口には、ガードマンやイヤホンをつけた職員が4、5名立ち並び、両腕を後ろに組み胸を反らせた姿勢で群衆の建物内への侵入を阻んでいる。衛兵然としたその威圧感に少し驚く。「お客さまの安全のため」という言葉の裏に本来はひそむべき“無用の責任は勘弁”という組織の本音が丸出し過ぎて、前衛コントのようなシュールさを感じた。なにしろ余震はまだ散発的に続いていて、“ガラスの船”の舷側のそと数十センチのエリアには、行き場を失った人々が群れているのだ。その真上に数十メートルのガラスの壁がそびえ建っている。主に会議室の多く入るガラス棟と広場に対面して建つホール棟群は地上階よりも2階3階のほうが広い構造だし、これで崩落規模の震動が来たらいったいここにいる何割が助かるだろう。しかしそうした想像が働くのは自分が目前の事態に何の責務も負っていないからで、何らかの職責を負ってこの場に遭遇した人々、つまり職員や駅員たちにとって重要なのは、仮にどれだけ違和感を覚えていたとしてもたぶん職責のほうなのだろう。だが結果として、その一見責務に篤い行動が客観的には単なる思考停止としか映らない、ということもまた十分あり得る話だ。ふとかつての福知山線脱線事故を思い起こす。あれなどまさに組織が要請する個々の職業意識の連鎖が、まだ若い一運転士の内面へと吹き溜まった挙句の速度超過ではなかったか。
広場のなかほどへと進み、土踏まずのあたりに疲れを感じたので近場にあったベンチへと腰をおろす。しばらく何するでもなくあたりを見回していると、屋外へ避難してたむろしているだけに見えていたビックカメラの店員たちの集団が、実はきちんと整列していたのに気がついた。10人ひと組の列が、よく見れば奥のほうまで20列近く並んで長方形の塊をつくっている。なんだろうとしばらく眺めていると、その集団のかたわらに大きなプラスチックケースが積まれていた。なかにはミネラルウォーターのペットボトルやスナック菓子、薬品類とおぼしきボックスや毛布などが入っている。ケースが積まれているといっても、それだけでは恐らく社員たちの分にしかならない。だが彼らが妙に気合が入った様子なのはなぜだろう。もしかしたら物資はもっと大量にあって、行き場をなくしたあたりの一般市民に配りだす意図でもあるのだろうか。まあそんなわけ、ないか。けれど、そういうことがあってもいいなと考える。ストック&フローを徹底した薄利多売を旨とする大型店舗の慌ただしい倉庫の物陰で、何年に一度も来ない出番をひっそりと緊急支援物資のひと山が待ち続ける。企業は利益を追求する。国は国益を最優先に行動する。だがその場合の利益国益とは本来何か。緊急時には見かけ上逆転しているような素振りを見せる集団こそ実は、より深い信念において揺るぎのない姿勢を貫いているといえる場合もあるだろう。
再び歩き始める。フォーラムの区画を北へ抜け、再び丸の内へ。ほんの2時間前とはまるで様子が変わっている。バス停は、バスの車内も外も黒山の人だかり。丸の内南口のそばに長蛇の列ができていて何かと思ってたどってみたら、列は中央口をまたいで丸の内北口のタクシー乗り場まで伸びていた。だが当のタクシーは一台も来ていない。だだっ広いタクシープールには虚しく寒風が吹いているだけだ。電車では帰れない、電話も通じない、歩いて帰るなど無謀、ゆえにタクシーを待つ列に並ぶほか打つ手がない、という思考経路をたどっているのだろう。だがその結果としてどうみても無意味な100メートル超のこの列に並ぶ選択を採ってしまうのは、純然たる思考停止にも思える。まだ混んではいるが来ているバスに並んでともかく都心を離れるとか、数ブロック歩いて流れのタクシーに期待をつなげるほうがマシではないか。まあ、五十歩百歩か。そうかもしれない。
少しからだの冷えを感じ始めたこともあり、いったん新丸ビルに入ってからだを温めることにする。ビルに入るとガラスの壁で隔てられた一区画で、多くの人が立ち尽して一方を見上げている。近づいてみると、彼らは壁2.5mほどの高さに嵌められた大型液晶の画面を、身動きじろぎもせず呆然と見つめていた。画面を見上げ、みなが呆然としている理由が即座にわかる。
……これは……なに?
つづく、かもしれず。
Job Description 18: 天文学者 【アレクサンドリア】
2011年3月28日 就職・転職
震災当日観るはずだった映画“アレクサンドリア”、ようやく観られたので久々に映画の感想書いてみます。
映画の舞台はローマ帝国末期、かのアレクサンドリア図書館や世界の七不思議の一つ、ファロス島の大灯台が現役だった時代のメトロポリス、アレクサンドリアです。主人公は実在した哲学者のヒュパティアで、彼女は数学者・天文学者としても当代一の才能があったと推測されています。“推測”と書いたのは、彼女の著作は現在すべて失われてしまっており、彼女に宛てられた手紙や周辺の学者・政治家たちの評価に拠るしか人となりを知る術がないためです。
この知的に研ぎ澄まされていてかつミステリアスな人物像を、主演のレイチェル・ワイズは見事に演じ切っていました。この女優の笑顔には、見る者の視線を引き込んで表情の内に束の間滞留させるような深みがあり、何かしら精神的に傷を負った役柄を演じさせると抜群に光るのですが、今回の作品では男中心の政治学問の現場や、迫り来る宗教的狂騒との緊張関係が全編にわたって続くため、まさにレイチェル・ワイズの長所ダダ漏れ作品になっていました。
当初この映画の存在を知ったとき、これは観ようと即決した最大の理由は、キリスト教徒によるアレクサンドリア図書館への襲撃が描かれていると伝えられていたからでした。これまで欧米の映画がキリスト教徒の集団を悪く描くときはたいてい、それでもキリスト教側にも一定の理を確保し、迫害する相手を文明の価値として露骨に下に置くような構図がありました。しかしこの時代随一のメトロポリスであったアレクサンドリアにおいて、果たしてそのような描き方がどれだけ可能なのか、そこに興味があったんですね。そして監督が“オープン・ユア・アイズ”や“海を飛ぶ夢”のアレハンドロ・アメナバールのスペイン映画、この2点だけでもうどんな失敗作だとしても入場料分の見応えは確信できました。
さて問題のキリスト教徒による破壊行為。生々しい暴力シーンそのものは抑えに抑えられていましたが、それだけに起きている出来事の凶暴性が深く響いてくるものがありました。図書館の門がいまにも暴徒たちに破られるという騒乱のさなかにあって、一つでも多くの書巻を持ち出したいけれど万巻の書に対して人手が足りなさすぎるなか、鋭い悲痛に身を裂かれながらも弟子たちに囲まれた自分が気丈に動かなくては救える書巻も救えなくなるという葛藤に苦しむレイチェル・ワイズの演技には、自分でも意外なほどに感情移入を誘われてしまいました。観客席で涙を滲ませる程度ならあるにしても、腰を落ち着けてそれを観ているのがつらいというほどの感情に襲われたのは稀有の体験でした。腕からこぼれ落ちてしまった書巻の一つ一つに、複数の賢者が一生を割いて見い出した叡智が詰まっている。それなのに、どうしても救えない。
ところでタイトルの“アレクサンドリア”、実はこれ日本限定の国内向けタイトルで、世界的には“Agora”として公開されているんですね。アゴラは古代ギリシアのポリスにおける広場や、そこで開かれる市民集会の意として日本でもよく知られていますね。古代ギリシアにルーツがあるだけあって、英語のほか多くのヨーロッパ系言語で同じ意味で用いられています。しかしこのタイトルの抱える含蓄はもう少し広く、スペイン語では名詞の“広場”のほか、動詞になるとagorarで“[迷信的に、主に災難を]予言する”、ポルトガル語では“現在”という意味を持っています。こう考えると、この作品の立ち位置がもう一段深まって見えてくる気がします。狂信的排他主義。理に沿わぬ暴動。無自覚の女性蔑視。通念に抗って己を貫く困難。主人公ヒュパティアの排斥を指示したアレクサンドリアの総司教キュリロスはその後、ローマ教会によって聖人に列せられています。考えさせられます。表出されているのはあくまで、“いま” なんですよね。その意味でも、かなりの名タイトル。
映画のなかでは、街の通りや広場のシーンから視点が上空へとあがり、ナイルや地中海を俯瞰したあと雲を抜け宇宙に浮かぶ地球の映像にまで引いていき、また元に戻るという視覚的往還が幾度か繰り返されます。このとき見せているアレクサンドリア周辺の地理や星座の配置は、精密な考証と計算を経て生み出されたCGによるもので現存しない姿です。それはそれで見応えのあるものだったし、観客の内面において人間の営みをミクロなものとして対象化させる効果を狙った監督の意図も巧く表現し切れていると思うのですが、ふとその地球大まで引いた映像のなかで地球が半回転して、日本列島の東北部をクローズアップしてゆくと、そこにあるはずのない1600年後の福島第一原発から伸びる白煙が映り込む。そんなシーンを連想せずにはいられませんでした。当分のあいだはそうやって、体験するあらゆるものの基底に震災の影が忍び入るような日々が続くのかもしれません。何年か、あるいはさらに。
"Agora" by Alejandro Amenabar / Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom / Xavi Gimenez [cinematography] / Guy Hendrix Dyas [production design] / Dario Marianelli [music performer] / 127min / Spain / 2009
映画の舞台はローマ帝国末期、かのアレクサンドリア図書館や世界の七不思議の一つ、ファロス島の大灯台が現役だった時代のメトロポリス、アレクサンドリアです。主人公は実在した哲学者のヒュパティアで、彼女は数学者・天文学者としても当代一の才能があったと推測されています。“推測”と書いたのは、彼女の著作は現在すべて失われてしまっており、彼女に宛てられた手紙や周辺の学者・政治家たちの評価に拠るしか人となりを知る術がないためです。
この知的に研ぎ澄まされていてかつミステリアスな人物像を、主演のレイチェル・ワイズは見事に演じ切っていました。この女優の笑顔には、見る者の視線を引き込んで表情の内に束の間滞留させるような深みがあり、何かしら精神的に傷を負った役柄を演じさせると抜群に光るのですが、今回の作品では男中心の政治学問の現場や、迫り来る宗教的狂騒との緊張関係が全編にわたって続くため、まさにレイチェル・ワイズの長所ダダ漏れ作品になっていました。
当初この映画の存在を知ったとき、これは観ようと即決した最大の理由は、キリスト教徒によるアレクサンドリア図書館への襲撃が描かれていると伝えられていたからでした。これまで欧米の映画がキリスト教徒の集団を悪く描くときはたいてい、それでもキリスト教側にも一定の理を確保し、迫害する相手を文明の価値として露骨に下に置くような構図がありました。しかしこの時代随一のメトロポリスであったアレクサンドリアにおいて、果たしてそのような描き方がどれだけ可能なのか、そこに興味があったんですね。そして監督が“オープン・ユア・アイズ”や“海を飛ぶ夢”のアレハンドロ・アメナバールのスペイン映画、この2点だけでもうどんな失敗作だとしても入場料分の見応えは確信できました。
さて問題のキリスト教徒による破壊行為。生々しい暴力シーンそのものは抑えに抑えられていましたが、それだけに起きている出来事の凶暴性が深く響いてくるものがありました。図書館の門がいまにも暴徒たちに破られるという騒乱のさなかにあって、一つでも多くの書巻を持ち出したいけれど万巻の書に対して人手が足りなさすぎるなか、鋭い悲痛に身を裂かれながらも弟子たちに囲まれた自分が気丈に動かなくては救える書巻も救えなくなるという葛藤に苦しむレイチェル・ワイズの演技には、自分でも意外なほどに感情移入を誘われてしまいました。観客席で涙を滲ませる程度ならあるにしても、腰を落ち着けてそれを観ているのがつらいというほどの感情に襲われたのは稀有の体験でした。腕からこぼれ落ちてしまった書巻の一つ一つに、複数の賢者が一生を割いて見い出した叡智が詰まっている。それなのに、どうしても救えない。
ところでタイトルの“アレクサンドリア”、実はこれ日本限定の国内向けタイトルで、世界的には“Agora”として公開されているんですね。アゴラは古代ギリシアのポリスにおける広場や、そこで開かれる市民集会の意として日本でもよく知られていますね。古代ギリシアにルーツがあるだけあって、英語のほか多くのヨーロッパ系言語で同じ意味で用いられています。しかしこのタイトルの抱える含蓄はもう少し広く、スペイン語では名詞の“広場”のほか、動詞になるとagorarで“[迷信的に、主に災難を]予言する”、ポルトガル語では“現在”という意味を持っています。こう考えると、この作品の立ち位置がもう一段深まって見えてくる気がします。狂信的排他主義。理に沿わぬ暴動。無自覚の女性蔑視。通念に抗って己を貫く困難。主人公ヒュパティアの排斥を指示したアレクサンドリアの総司教キュリロスはその後、ローマ教会によって聖人に列せられています。考えさせられます。表出されているのはあくまで、“いま” なんですよね。その意味でも、かなりの名タイトル。
映画のなかでは、街の通りや広場のシーンから視点が上空へとあがり、ナイルや地中海を俯瞰したあと雲を抜け宇宙に浮かぶ地球の映像にまで引いていき、また元に戻るという視覚的往還が幾度か繰り返されます。このとき見せているアレクサンドリア周辺の地理や星座の配置は、精密な考証と計算を経て生み出されたCGによるもので現存しない姿です。それはそれで見応えのあるものだったし、観客の内面において人間の営みをミクロなものとして対象化させる効果を狙った監督の意図も巧く表現し切れていると思うのですが、ふとその地球大まで引いた映像のなかで地球が半回転して、日本列島の東北部をクローズアップしてゆくと、そこにあるはずのない1600年後の福島第一原発から伸びる白煙が映り込む。そんなシーンを連想せずにはいられませんでした。当分のあいだはそうやって、体験するあらゆるものの基底に震災の影が忍び入るような日々が続くのかもしれません。何年か、あるいはさらに。
"Agora" by Alejandro Amenabar / Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom / Xavi Gimenez [cinematography] / Guy Hendrix Dyas [production design] / Dario Marianelli [music performer] / 127min / Spain / 2009
2011.3.11メモランダム part4 <16時-16時半 数寄屋橋-日比谷>
2011年3月25日 陸沈
この身のうちに生じる感覚や思考を、当然のごとく受け入れることに初めて疑問を持ったのは何歳くらいのことだろう。まぶたを閉じると勝手に巡りだすイメージや感情の動きを、ひとごとのように眺める自分がいることにいつの頃からか気づき出していた。小学校でも保育園でも、「ぼーっとしてないで!」とよく先生から叱られたのを覚えている。そう言われるときに限って内面的にはかなり忙しかったりするものだから、いつもなんだか理不尽さを感じていた。いま視界を占めるこの雑踏を構成する一人ひとりが、この自分同様に輪郭すら定かでない感覚や思考を携えていることが、この歳になってなおきちんと了解できていない気がする。あるいは多くの人にとってのそれは、はっきりとした輪郭があるのだろうか。うまく想像できない。
数寄屋橋の交差点近くまで戻ったとき、突如拡声器によるアナウンスが始まった。顔をあげると、交差点の十字路を行き交う雑踏や車の群れが目に入る。拡声器の声は、人だかりを越えて交差点向かいの奥に建つ、数寄屋橋交番からのものだとわかる。特徴的な赤レンガの尖塔屋根にでかでかと“KOBAN”の文字。パトカー側面に際立つ“POLICE”表示とは異なり、“KOBAN”のほうは何年たっても違和感が拭えない。音から銭形平次的ニュアンスも混じり込み、外国の色々間違ってるサムライ映画みたいな心象が沸き起こる。実直さが滑稽さをなぜか呼び込んでしまうお馴染みの回路も、このように表出してくると憎めない。そのKOBANのてっぺんあたりから周囲に振り撒かれているアナウンスは、中年男性の低くしわがれた声で電車が止まったことを告げている。男の声は止まった路線の名を一つ一つ挙げていく。
「JR山手線全線、京浜東北線全線、東海道線全線、総武線全線・・・・東京メトロ銀座線全線、日比谷線全線、……都営三田線全線、浅草線全線……」
要するに、全部だ。そして最後のひとことが、致命的にひとの波を揺るがせてゆく。
「……JR各線は、全線で終日運休の見通しです。」
嘘だろう、とはじめは思った。恐らくこれを耳にした通行人の誰もがそう思ったのではないか。運行をあきらめるタイミングがいくらなんでも早過ぎるし、それに比べて決断の影響が大きすぎる、ように思えた。当のJRではなく警察による告知だし、言句の行き違いが起きたか、とも。だが直後に、嫌な予感が心中をかすめる。つい先ほど見た、パトカーが有楽町駅への小道をふさぐ光景が脳裡をよぎった。あのとき道を封鎖するほどの事態は確認できなかったが、いま思えば予兆はあった。有楽町駅前の車道に、電車の運行再開を待つ人々が一部あふれ始めていたのだ。手持ち無沙汰に数人で世間話を交わすグループの群れが歩道からはみ出し、縁石のブロックにしゃがみ込んで携帯画面を覗き込んでいるひとも散見した。周辺から駅へと向かうひとの流れが、そこへ怒涛のごとく注ぎ込んでいる。もしいま車両が列をなして加わっていたら、ひとも車も身動きがとれなくなっておかしくない。
あのパトカーによる封鎖は、それを読み込んでいたことになる。現下の異常に対する逐次対応ではなく、そうした防災対策がもともとあったということだ。そこから何が導き出せるか。《震度~以上であれば、~計画を施行》というような約定が、あらかじめ鉄道や警察等の各種公共機関のあいだで交わされ、いままさにその発動下にあると考えたほうが筋が通る。そうなれば日本人が集団化した際に発揮される持ち前のリジッドさから、組織体ごとの判断よりも計画全体の着実な施行が優先されるのは間違いない。つまり、危険性の如何に関わらず、
“JRは、ほんとうに終日動かない可能性高し”
となる。いよいよ極まってきた。といって周辺の人々に、「電車待っても無駄ですね、本気で再開しませんよ」とはむろん説かない。これは個人の勝手な憶測に過ぎないし、その憶測によれば《利用客に迫る危険が電車を終日止めさせる》のではないからだ。待ち続ければ寒い思いはするだろうが、たぶんそれだけの話でしかない。というわけで、一人ひっそりと場を離れる。
けれどそうしてもし憶測通りの横断的連携がこうも速やかに図られているならば、その結果として都心の特定区画にひとが集中してゆくこの状況は、果たして立案者の予見のうちにあるのだろうか。“仕方ない”、“しようがない”という人々のあきらめによって受け流され、忘却されゆく事象のうちに、特定の個人や集団のみに都合の良い事情が潜むというのはよくある話だ。気づきにくいだけで、恐らく身のまわりじゅうにあるのだろう。そして時にはそれが、大量の人々を決定的な悲劇へと巻き込んでいく。国や企業が起こす大事故の本質はそこにある。良いほうに流れているのか、悪いほうに流れているのか。すべてが進行中のさなかにあってそこを見極めるのは結局、個々人の判断力に拠るしかない。
首都高ガード下を再度くぐる。ガード下ショッピングモールの商売熱がセールのワゴン数台分、歩道へと乗り出している。しかしいまやワゴン上の商品に目を遊ばせる通行人は一人もいない。たとえばこの数寄屋橋交番の背後に長く横たわる、首都高ガード下の古いショッピングモール。高架道路に沿って蛇のように伸びるこの数寄屋橋のモール街は、実は蛇行線がそのまま千代田区と中央区の境界線に相当して、かつ税制的にはどちらにも属していないという話がある。首都高が開通した東京オリンピック以来ずっと、税収の行き先が問われないまま自民党系の某派閥の懐へ流れ続け、それを知る古株メディア関係者も多かったがタブー視されたままみな引退を迎えている、という類の都市伝説。数寄屋橋という橋が現存しないことからもわかるように、この蛇行線の地下部分にはいまも暗渠化された河が流れており、河幅の中央に引かれた区境は理念上の存在でしかなかったという経緯に、この話の暗さと多重性がより強く印象づけられた記憶がある。個別の真偽はともかく、そうした風に各種の利権構造がまだら状に散らばるのが都心の本当の姿なのだろう。土地関連、電気やガス、通信、物流等々、生活のあらゆる面で支払う代価の配当先を熟知する者など恐らく皆無だし、あるいは古来よりそれらを暗黙の了解としてきたのが人間社会というものなのかもしれない。
駅とは別の方向、JRのガード下をくぐって日比谷へとさらに歩く。ならばいまこの異常事態のさなかで、つまりそれぞれがそれぞれにまず己の保全を優先して動くだろう状況下で、本来の異常さとは別の理由がさらなる混乱を生むとすれば、何が起こり得るだろう。日比谷公園へ向かうことを思いつくが、周囲のビルからの避難者に混じってもできることはないので却下、右折して北上開始。道路の向こうに望める皇居前広場の樹々はひとの混乱をよそにいつも通り整然と並び、濃緑のシルエットを作っている。背景の灰空はビルの谷間に挟まれているせいか、いつもより高く見える。この冬空のもと、関東平野一帯で大量の鉄道車両が全停止している光景が脳裡に浮かぶ。車両はいずれもエンジン音を鎮め、台車部分から弱々しく水蒸気を吐き出している。排気口から水滴が一粒したたり落ちる。車輪によって磨かれたレールの鏡面が、落下した水滴を弾き飛ばす。銀色の鏡面には、遠く離れたホームで電車を待つ人々の立ち姿がミクロに映り込んでいる。
家まで歩く可能性を視野に入れてまずは大手町を北へ抜け、神田を目指すことにした。
つづく、かもしれず。
数寄屋橋の交差点近くまで戻ったとき、突如拡声器によるアナウンスが始まった。顔をあげると、交差点の十字路を行き交う雑踏や車の群れが目に入る。拡声器の声は、人だかりを越えて交差点向かいの奥に建つ、数寄屋橋交番からのものだとわかる。特徴的な赤レンガの尖塔屋根にでかでかと“KOBAN”の文字。パトカー側面に際立つ“POLICE”表示とは異なり、“KOBAN”のほうは何年たっても違和感が拭えない。音から銭形平次的ニュアンスも混じり込み、外国の色々間違ってるサムライ映画みたいな心象が沸き起こる。実直さが滑稽さをなぜか呼び込んでしまうお馴染みの回路も、このように表出してくると憎めない。そのKOBANのてっぺんあたりから周囲に振り撒かれているアナウンスは、中年男性の低くしわがれた声で電車が止まったことを告げている。男の声は止まった路線の名を一つ一つ挙げていく。
「JR山手線全線、京浜東北線全線、東海道線全線、総武線全線・・・・東京メトロ銀座線全線、日比谷線全線、……都営三田線全線、浅草線全線……」
要するに、全部だ。そして最後のひとことが、致命的にひとの波を揺るがせてゆく。
「……JR各線は、全線で終日運休の見通しです。」
嘘だろう、とはじめは思った。恐らくこれを耳にした通行人の誰もがそう思ったのではないか。運行をあきらめるタイミングがいくらなんでも早過ぎるし、それに比べて決断の影響が大きすぎる、ように思えた。当のJRではなく警察による告知だし、言句の行き違いが起きたか、とも。だが直後に、嫌な予感が心中をかすめる。つい先ほど見た、パトカーが有楽町駅への小道をふさぐ光景が脳裡をよぎった。あのとき道を封鎖するほどの事態は確認できなかったが、いま思えば予兆はあった。有楽町駅前の車道に、電車の運行再開を待つ人々が一部あふれ始めていたのだ。手持ち無沙汰に数人で世間話を交わすグループの群れが歩道からはみ出し、縁石のブロックにしゃがみ込んで携帯画面を覗き込んでいるひとも散見した。周辺から駅へと向かうひとの流れが、そこへ怒涛のごとく注ぎ込んでいる。もしいま車両が列をなして加わっていたら、ひとも車も身動きがとれなくなっておかしくない。
あのパトカーによる封鎖は、それを読み込んでいたことになる。現下の異常に対する逐次対応ではなく、そうした防災対策がもともとあったということだ。そこから何が導き出せるか。《震度~以上であれば、~計画を施行》というような約定が、あらかじめ鉄道や警察等の各種公共機関のあいだで交わされ、いままさにその発動下にあると考えたほうが筋が通る。そうなれば日本人が集団化した際に発揮される持ち前のリジッドさから、組織体ごとの判断よりも計画全体の着実な施行が優先されるのは間違いない。つまり、危険性の如何に関わらず、
“JRは、ほんとうに終日動かない可能性高し”
となる。いよいよ極まってきた。といって周辺の人々に、「電車待っても無駄ですね、本気で再開しませんよ」とはむろん説かない。これは個人の勝手な憶測に過ぎないし、その憶測によれば《利用客に迫る危険が電車を終日止めさせる》のではないからだ。待ち続ければ寒い思いはするだろうが、たぶんそれだけの話でしかない。というわけで、一人ひっそりと場を離れる。
けれどそうしてもし憶測通りの横断的連携がこうも速やかに図られているならば、その結果として都心の特定区画にひとが集中してゆくこの状況は、果たして立案者の予見のうちにあるのだろうか。“仕方ない”、“しようがない”という人々のあきらめによって受け流され、忘却されゆく事象のうちに、特定の個人や集団のみに都合の良い事情が潜むというのはよくある話だ。気づきにくいだけで、恐らく身のまわりじゅうにあるのだろう。そして時にはそれが、大量の人々を決定的な悲劇へと巻き込んでいく。国や企業が起こす大事故の本質はそこにある。良いほうに流れているのか、悪いほうに流れているのか。すべてが進行中のさなかにあってそこを見極めるのは結局、個々人の判断力に拠るしかない。
首都高ガード下を再度くぐる。ガード下ショッピングモールの商売熱がセールのワゴン数台分、歩道へと乗り出している。しかしいまやワゴン上の商品に目を遊ばせる通行人は一人もいない。たとえばこの数寄屋橋交番の背後に長く横たわる、首都高ガード下の古いショッピングモール。高架道路に沿って蛇のように伸びるこの数寄屋橋のモール街は、実は蛇行線がそのまま千代田区と中央区の境界線に相当して、かつ税制的にはどちらにも属していないという話がある。首都高が開通した東京オリンピック以来ずっと、税収の行き先が問われないまま自民党系の某派閥の懐へ流れ続け、それを知る古株メディア関係者も多かったがタブー視されたままみな引退を迎えている、という類の都市伝説。数寄屋橋という橋が現存しないことからもわかるように、この蛇行線の地下部分にはいまも暗渠化された河が流れており、河幅の中央に引かれた区境は理念上の存在でしかなかったという経緯に、この話の暗さと多重性がより強く印象づけられた記憶がある。個別の真偽はともかく、そうした風に各種の利権構造がまだら状に散らばるのが都心の本当の姿なのだろう。土地関連、電気やガス、通信、物流等々、生活のあらゆる面で支払う代価の配当先を熟知する者など恐らく皆無だし、あるいは古来よりそれらを暗黙の了解としてきたのが人間社会というものなのかもしれない。
駅とは別の方向、JRのガード下をくぐって日比谷へとさらに歩く。ならばいまこの異常事態のさなかで、つまりそれぞれがそれぞれにまず己の保全を優先して動くだろう状況下で、本来の異常さとは別の理由がさらなる混乱を生むとすれば、何が起こり得るだろう。日比谷公園へ向かうことを思いつくが、周囲のビルからの避難者に混じってもできることはないので却下、右折して北上開始。道路の向こうに望める皇居前広場の樹々はひとの混乱をよそにいつも通り整然と並び、濃緑のシルエットを作っている。背景の灰空はビルの谷間に挟まれているせいか、いつもより高く見える。この冬空のもと、関東平野一帯で大量の鉄道車両が全停止している光景が脳裡に浮かぶ。車両はいずれもエンジン音を鎮め、台車部分から弱々しく水蒸気を吐き出している。排気口から水滴が一粒したたり落ちる。車輪によって磨かれたレールの鏡面が、落下した水滴を弾き飛ばす。銀色の鏡面には、遠く離れたホームで電車を待つ人々の立ち姿がミクロに映り込んでいる。
家まで歩く可能性を視野に入れてまずは大手町を北へ抜け、神田を目指すことにした。
つづく、かもしれず。
東京駅の八重洲南口には長距離のバスターミナルがあって、中学高校時代にはここから夜行バスに乗ってよく一人旅をやっていた。下北半島や山口の秋吉台へ出かけて手前勝手に世界の果てを感じたり、民宿のおばあちゃんやユースホステルのおじちゃんがとても親切に接してくれたのを覚えている。彼らはもしかしたら、一人で家出してきた可能性をわたしに見ていたのかもしれないとあとになって思うのだけど、実際学校はサボっていたし、親に行き先を告げないこともしばしばだったから大差はなかった。
あの頃に比べればいま世界はぐんと広くなっている。けれど、本当のところは逆に狭くなってしまったのかもとも、時々感じる。いまもバスターミナルは同じ八重洲南口に変わらずあって、売店やチケット売り場もだいたい同じ配置なのだけど、サイズがずいぶん小さくなって見えてしまう。自分が身体的に成長したせいだろうけど、このバスターミナルを抜けて八重洲ブックセンターへ向かうときは何だかいつも、恥ずかしさにも罪悪感にも似た微妙な感覚に襲われる。からだ相応、年齢相応の人間的成長をきちんと重ねて来れたのかと考えるとなかなか怪しいというか、正直その種の自信はあまりない。
ともあれその八重洲ブックセンターから外堀通りをまっすぐ南下して歩き、パトカーで車両をさえぎられた小道を有楽町方面へ曲がる。このガード下には首都高の高架に沿って細長く古いモール街があって昔から賑わっているのだけど、きょうはその賑わいとも関係なく人通りの多さが目立つ。有楽町の駅へ近づくにつれやけにひとの数が増えだしたため、ああ電車が一時運休になったのかもしれないと、このときようやく見当がつき始めた。しかし目下わたしには無縁のトラブルではある。なにせこれから映画観るんだし、電車なぞ半刻でも一刻でも停まるがよいぞよきにはからへ。と、このときは大して気にもとめず。阿呆である。
というわけで、有楽町駅前の交通会館にある三省堂書店着。少し覗いて去るつもりだったが、だがしかし。ここは丸善や八重洲ブックセンターのように2階以上だけでなく、1階も閉鎖、つまり閉店状態になっていた。むう。仕方ないので本日の最終目的地、丸の内ピカデリーが入る有楽町マリオンへと踵を返す。
マリオンの映画館群の券売窓口は大きく二箇所に別れていて、マリオン正面の吹き抜け通路を入って両サイドにある表の窓口はいつも騒々しいために、高校生の頃からずっと建物脇の小道に面した裏の窓口を愛用している。天候によっては買った券が瞬時に風雨に晒されるという、素人にはおすすめできない過酷な窓口なのだけれど、どうもきょうは様子が変である。丸の内ルーブルの券売ブースの店員さんはドアを開け放って数人で歓談してるし、丸の内ピカデリーのブースはもう上映開始10分前だというのになんとカーテンを降ろしている。これは嫌な予感がする。というか、オワタ感満載である。念のため表側の窓口へ。やはりひとがいない。いや、関係者らしき人物がひとり、付近の柱の物陰に立ってあたりを睥睨していた。にじり寄っておもむろに問い詰める。すると返す刀が一閃、「4時の回は中止です。」 ささやかなきょうの楽しみ、終了。
2秒ほどすべてに絶望したものの、次の瞬間には脳みそが今後の行動プログラムを弾き出す。いや、弾き出さない。電車とまってるんだった。思考フリーズ、立ち尽くす。とりあえず、マリオンの吹き抜け通路を数寄屋橋の交差点側へ、とぼとぼ抜ける。建物を抜けたところで、天空より鐘の音が鳴り響く。何かと思ったら、4時ちょうどになって頭上の仕掛け時計が動き始めたところだった。時計盤がせり上がり、黄金の球体に立つ黄金の幼児が空中へとせり出してくる。彼らが実は全身に金箔を塗られて強制的に児童労働させられている本物の幼児だったら、ホラーだ。などと妄想を駆け巡らせつつそのカクカクした演奏をしばらく見上げ、そのまま首をかたむけJRの高架線路へと視線を振り向ける。ああ、変なところで緊急停車している東海道新幹線の車両が見える。からだの向きを変えて逆方向を見る。なぜかうっすらと、あたりが白く煙ってみえる。マリオン本館と別館のあいだのそう広くはないビルの谷間に、ヘルメットをかぶった作業員が100人近くたむろしている。それだけの人数になると、さすがに異様だ。付近にこれといって工事現場は見当たらない。空気のなかに少しだけ、ガスの刺激臭が嗅ぎ取れる。
うん、これは思っている以上におおごとかもしれません。と、このときようやく事態の全体像へと関心を持ちはじめた。だが当面の予定が消えしかも電車が動かないという状況にただちに向きあう気にもなれず、滅多に打たない携帯メールを友人に送ってみる。なぜかメール送信中に回線が切れてしまう。再送信。無駄。3度目でようやく送れたが、こういうときは‘古い機種だしね’と即座にあきらめる習慣が身についてすでに久しい。ゆえに他のひともみな電話が不通状態にあるなどと、まるで想像さえしなかった。このとき友人に送ったメールの文面は以下のごとく。
「お金おろしに東京きたら、じしんおきてみるきだった映画中止、本屋閉店、電車とまた。いみふ」
超絶脳天気だった。
いい加減おとなになれよ、とは思う。他に言うべきことはないのかと。それ自体はまっとうなこの‘おとなになれよ’という思いが常態化した焦りとなってから、もう何年がたつだろう。けれどなぜか、行動に結びつくことがない。だってほら、いまもからだはどんどん銀座方面へと歩き出している。なんの用事もないのに。にわかに増加したひとの流れは、自分とは逆にみな駅方向へと向かっている。この状況下ではおそらく、それが最も正しい一般解なのだろう。
数寄屋橋の交差点を渡って銀座SONYビルを見上げたとき、歩いて自宅まで帰る計算を頭のなかで始めている自分に気がついた。少なくともこの交差点から見渡せる、夕暮れ時の街の電飾はいつも通り鮮やかで、ひとも車もここではいつも通りにひしめきあっている。目に見える日常の光景と、目には見えない不穏さとのこのギャップは何だろう。まあ結局、なるようにしかならなさそうだ。思う通りにやるしかない。正しいとか、間違いとかいう問題ではたぶんない。体は動く。頭も働く。それだけでも十分な資産だろう。あとはやり抜けるかどうかだけが問題だ。
マフラーを忘れて家を出たことが、このとき初めて悔やまれた。そのまま銀座へと進むうちに思い浮かんでくるものがあり、踵を返して日比谷方面へ歩き始めることにする。
あの頃に比べればいま世界はぐんと広くなっている。けれど、本当のところは逆に狭くなってしまったのかもとも、時々感じる。いまもバスターミナルは同じ八重洲南口に変わらずあって、売店やチケット売り場もだいたい同じ配置なのだけど、サイズがずいぶん小さくなって見えてしまう。自分が身体的に成長したせいだろうけど、このバスターミナルを抜けて八重洲ブックセンターへ向かうときは何だかいつも、恥ずかしさにも罪悪感にも似た微妙な感覚に襲われる。からだ相応、年齢相応の人間的成長をきちんと重ねて来れたのかと考えるとなかなか怪しいというか、正直その種の自信はあまりない。
ともあれその八重洲ブックセンターから外堀通りをまっすぐ南下して歩き、パトカーで車両をさえぎられた小道を有楽町方面へ曲がる。このガード下には首都高の高架に沿って細長く古いモール街があって昔から賑わっているのだけど、きょうはその賑わいとも関係なく人通りの多さが目立つ。有楽町の駅へ近づくにつれやけにひとの数が増えだしたため、ああ電車が一時運休になったのかもしれないと、このときようやく見当がつき始めた。しかし目下わたしには無縁のトラブルではある。なにせこれから映画観るんだし、電車なぞ半刻でも一刻でも停まるがよいぞよきにはからへ。と、このときは大して気にもとめず。阿呆である。
というわけで、有楽町駅前の交通会館にある三省堂書店着。少し覗いて去るつもりだったが、だがしかし。ここは丸善や八重洲ブックセンターのように2階以上だけでなく、1階も閉鎖、つまり閉店状態になっていた。むう。仕方ないので本日の最終目的地、丸の内ピカデリーが入る有楽町マリオンへと踵を返す。
マリオンの映画館群の券売窓口は大きく二箇所に別れていて、マリオン正面の吹き抜け通路を入って両サイドにある表の窓口はいつも騒々しいために、高校生の頃からずっと建物脇の小道に面した裏の窓口を愛用している。天候によっては買った券が瞬時に風雨に晒されるという、素人にはおすすめできない過酷な窓口なのだけれど、どうもきょうは様子が変である。丸の内ルーブルの券売ブースの店員さんはドアを開け放って数人で歓談してるし、丸の内ピカデリーのブースはもう上映開始10分前だというのになんとカーテンを降ろしている。これは嫌な予感がする。というか、オワタ感満載である。念のため表側の窓口へ。やはりひとがいない。いや、関係者らしき人物がひとり、付近の柱の物陰に立ってあたりを睥睨していた。にじり寄っておもむろに問い詰める。すると返す刀が一閃、「4時の回は中止です。」 ささやかなきょうの楽しみ、終了。
2秒ほどすべてに絶望したものの、次の瞬間には脳みそが今後の行動プログラムを弾き出す。いや、弾き出さない。電車とまってるんだった。思考フリーズ、立ち尽くす。とりあえず、マリオンの吹き抜け通路を数寄屋橋の交差点側へ、とぼとぼ抜ける。建物を抜けたところで、天空より鐘の音が鳴り響く。何かと思ったら、4時ちょうどになって頭上の仕掛け時計が動き始めたところだった。時計盤がせり上がり、黄金の球体に立つ黄金の幼児が空中へとせり出してくる。彼らが実は全身に金箔を塗られて強制的に児童労働させられている本物の幼児だったら、ホラーだ。などと妄想を駆け巡らせつつそのカクカクした演奏をしばらく見上げ、そのまま首をかたむけJRの高架線路へと視線を振り向ける。ああ、変なところで緊急停車している東海道新幹線の車両が見える。からだの向きを変えて逆方向を見る。なぜかうっすらと、あたりが白く煙ってみえる。マリオン本館と別館のあいだのそう広くはないビルの谷間に、ヘルメットをかぶった作業員が100人近くたむろしている。それだけの人数になると、さすがに異様だ。付近にこれといって工事現場は見当たらない。空気のなかに少しだけ、ガスの刺激臭が嗅ぎ取れる。
うん、これは思っている以上におおごとかもしれません。と、このときようやく事態の全体像へと関心を持ちはじめた。だが当面の予定が消えしかも電車が動かないという状況にただちに向きあう気にもなれず、滅多に打たない携帯メールを友人に送ってみる。なぜかメール送信中に回線が切れてしまう。再送信。無駄。3度目でようやく送れたが、こういうときは‘古い機種だしね’と即座にあきらめる習慣が身についてすでに久しい。ゆえに他のひともみな電話が不通状態にあるなどと、まるで想像さえしなかった。このとき友人に送ったメールの文面は以下のごとく。
「お金おろしに東京きたら、じしんおきてみるきだった映画中止、本屋閉店、電車とまた。いみふ」
超絶脳天気だった。
いい加減おとなになれよ、とは思う。他に言うべきことはないのかと。それ自体はまっとうなこの‘おとなになれよ’という思いが常態化した焦りとなってから、もう何年がたつだろう。けれどなぜか、行動に結びつくことがない。だってほら、いまもからだはどんどん銀座方面へと歩き出している。なんの用事もないのに。にわかに増加したひとの流れは、自分とは逆にみな駅方向へと向かっている。この状況下ではおそらく、それが最も正しい一般解なのだろう。
数寄屋橋の交差点を渡って銀座SONYビルを見上げたとき、歩いて自宅まで帰る計算を頭のなかで始めている自分に気がついた。少なくともこの交差点から見渡せる、夕暮れ時の街の電飾はいつも通り鮮やかで、ひとも車もここではいつも通りにひしめきあっている。目に見える日常の光景と、目には見えない不穏さとのこのギャップは何だろう。まあ結局、なるようにしかならなさそうだ。思う通りにやるしかない。正しいとか、間違いとかいう問題ではたぶんない。体は動く。頭も働く。それだけでも十分な資産だろう。あとはやり抜けるかどうかだけが問題だ。
マフラーを忘れて家を出たことが、このとき初めて悔やまれた。そのまま銀座へと進むうちに思い浮かんでくるものがあり、踵を返して日比谷方面へ歩き始めることにする。
海外メディア震災報道を軸にmixi更新始めました。
2011年3月15日 陸沈
昨夜から今朝にかけて、福島原発を中心にかなり際どい局面が展開されました。今後も同様の状況が続く可能性は高く、個人的な情報の取捨選択と逐次雑感の開示をミクシィの方で行うことにしました。ぜひ一度アクセスして下さいませ。
登録名: goodbye
登録ニックネーム: ぐぴ
prof URL: http://mixi.jp/show_profile.pl?id=8760128
基本的に国内地上波TV・ラジオが報じないor先行する情報のURL提示と日本語要約、まとめが中心になる予定。
当分のあいだマイミク申請はすべて受け付けます。(全体公開設定なので、マイミクにならずとも読めます。) 自己満足といえばそれまでだけれど、出来る範囲のことは自力で考えて選択したいし、その経過を共有できるひとがいるならそれはありがたいことです。よろしくお願いします。
なお当ブログは今後もスタンスを変えず継続します。ではまた再見。
以下は昨夜から今朝にかけての書き込み例です。
●
BBC報道: 日本政府は安全性を強調するも、米空母は沖合い160kmで低レヴェルの放射線を検出、当該エリアから離脱済み。
The US said it had moved one of its aircraft carriers from the area after detecting low radiation 100 miles offshore.
http://bbc.in/g9kZC4
これ、BBCがアジアトップにおいてる記事ね。日本のメディアは現在ガン無視してる情報です。多少市民を被爆させてもパニック防止を優先する政府圧力の可能性あり。(※14日深夜時点)
ちなみに原子力関連については、TVでは日テレが唯一政府広報に反した報道をここ数日続けてます。それでも海外メディアに比べると半日遅れ。
●
被爆した未来の自分を想像する。うまく想像できない。津波を甘くみてまだ作業できると家に残り、家ごと呑み込まれた人たちのことを想像する。これなら何とか想像できる。そして自分たちは今、まさに同じ状況下にあるのかも知れない。
●
福島第一原発2号機、放射性物質を高濃度に含む蒸気の外気への放出実施 http://goo.gl/zgzHS
●
ロイター発: 米原子力委、日本政府が米政府に原子炉冷却を巡って正式な救援要請
U.S. nuclear regulatory commission says Japanese government formally asks U.S. for help with cooling nuclear reactors
http://www.reuters.com/
●
時事ドットコム: IAEA専門家の派遣要請=福島原発事故−日本政府 http://htn.to/r4cTW9
国民向けには「心配ない」と言いつつ、手当たり次第にヘルプ求めだしてます。妥当といえば妥当、けれどミクロの主観視点ではなんか儚い。
●
陸上自衛隊「中央特殊武器防護隊」 オフサイトセンターから退避検討 http://bit.ly/h8eSGh
●
BBC報道: 福島原発の現状をめぐる Q&A 全体的に安心できる要素の提示が多め http://j.mp/hletSu
●
建築基準法で定められている24時間換気をやめる操作 http://ow.ly/4eAzH 気になるひとがいれば。 うちはまだやらないけど、一応メモ。(
●
横須賀、川崎、放射線量が6~8倍に http://nifty.jp/dQeNPZ
東京で20倍の観測 さいたまは40倍 http://bit.ly/f1ISG7
茨城県内で自然界の100倍放射線量 http://bit.ly/fCFQjQ
他に数時間前に茨城で上昇とか千葉3倍とかあったけど、測定値関連のつぶやきは多分これで打ち止め。理由はmixi日記のほう参照のこと。
●
原発関連の具体的な情報分析を日本語で聞きたいひとへのお薦めは、
原子力資料情報室CNIC: http://www.ustream.tv/channel/cnic-news
の録画群にある後藤政志氏(元原子炉格納容器設計者)の解説が説得的。CNICは従来反原発の立場なので、マスメディアとは逆のバイアスが掛かり得る点でも情報のバランシングの面でも有効。現在進行形で随時情報発信を続けている。
登録名: goodbye
登録ニックネーム: ぐぴ
prof URL: http://mixi.jp/show_profile.pl?id=8760128
基本的に国内地上波TV・ラジオが報じないor先行する情報のURL提示と日本語要約、まとめが中心になる予定。
当分のあいだマイミク申請はすべて受け付けます。(全体公開設定なので、マイミクにならずとも読めます。) 自己満足といえばそれまでだけれど、出来る範囲のことは自力で考えて選択したいし、その経過を共有できるひとがいるならそれはありがたいことです。よろしくお願いします。
なお当ブログは今後もスタンスを変えず継続します。ではまた再見。
以下は昨夜から今朝にかけての書き込み例です。
●
BBC報道: 日本政府は安全性を強調するも、米空母は沖合い160kmで低レヴェルの放射線を検出、当該エリアから離脱済み。
The US said it had moved one of its aircraft carriers from the area after detecting low radiation 100 miles offshore.
http://bbc.in/g9kZC4
これ、BBCがアジアトップにおいてる記事ね。日本のメディアは現在ガン無視してる情報です。多少市民を被爆させてもパニック防止を優先する政府圧力の可能性あり。(※14日深夜時点)
ちなみに原子力関連については、TVでは日テレが唯一政府広報に反した報道をここ数日続けてます。それでも海外メディアに比べると半日遅れ。
●
被爆した未来の自分を想像する。うまく想像できない。津波を甘くみてまだ作業できると家に残り、家ごと呑み込まれた人たちのことを想像する。これなら何とか想像できる。そして自分たちは今、まさに同じ状況下にあるのかも知れない。
●
福島第一原発2号機、放射性物質を高濃度に含む蒸気の外気への放出実施 http://goo.gl/zgzHS
●
ロイター発: 米原子力委、日本政府が米政府に原子炉冷却を巡って正式な救援要請
U.S. nuclear regulatory commission says Japanese government formally asks U.S. for help with cooling nuclear reactors
http://www.reuters.com/
●
時事ドットコム: IAEA専門家の派遣要請=福島原発事故−日本政府 http://htn.to/r4cTW9
国民向けには「心配ない」と言いつつ、手当たり次第にヘルプ求めだしてます。妥当といえば妥当、けれどミクロの主観視点ではなんか儚い。
●
陸上自衛隊「中央特殊武器防護隊」 オフサイトセンターから退避検討 http://bit.ly/h8eSGh
●
BBC報道: 福島原発の現状をめぐる Q&A 全体的に安心できる要素の提示が多め http://j.mp/hletSu
●
建築基準法で定められている24時間換気をやめる操作 http://ow.ly/4eAzH 気になるひとがいれば。 うちはまだやらないけど、一応メモ。(
●
横須賀、川崎、放射線量が6~8倍に http://nifty.jp/dQeNPZ
東京で20倍の観測 さいたまは40倍 http://bit.ly/f1ISG7
茨城県内で自然界の100倍放射線量 http://bit.ly/fCFQjQ
他に数時間前に茨城で上昇とか千葉3倍とかあったけど、測定値関連のつぶやきは多分これで打ち止め。理由はmixi日記のほう参照のこと。
●
原発関連の具体的な情報分析を日本語で聞きたいひとへのお薦めは、
原子力資料情報室CNIC: http://www.ustream.tv/channel/cnic-news
の録画群にある後藤政志氏(元原子炉格納容器設計者)の解説が説得的。CNICは従来反原発の立場なので、マスメディアとは逆のバイアスが掛かり得る点でも情報のバランシングの面でも有効。現在進行形で随時情報発信を続けている。
交差点を渡り、丸の内ロータリー北端の歩道を回って商業施設OAZOの入り口へ。東京駅北口改札への横断歩道を過ぎるあたりで、たむろしている人々が妙に多いことを不思議に感じだす。この数年でずいぶん賑やかになったとはいえ根本は無味乾燥なオフィス街の、しかも平日の昼下がりだ。目的を持って歩くスーツ姿の人間以外を惹きつける要素はあまりないはず。だがOAZOの建物に入ってその謎はすぐに解けた。上階へのエスカレーターに規制線が張られて近づけない。丸善などは、2階以上の店内からすでに客の追い出しを完了させていた。
映画は4時過ぎからなので、銀座まで歩くことを考えてもだいぶ間がある。都心のどこであれ本屋をはしごするのが時間潰しの基本ルートなのだが、初手で狂った。どうしようかとビルの吹き抜けロビーでしばらく人の流れを眺めていると、震動再来。高い天井から吊り下げられた照明や装飾の類が一斉に踊る。ロビーの人々、みな騒然。このとき群衆単位の動揺を目にしてようやく、体感はできないどこか遠方で予想外のおおごとが起きている可能性に気づく。あくまで可能性のレヴェル。まさかね。
再度、余震。広いロビーにたむろしていた集団が大きく二手に別れてゆく。足早にビルの外へと避難する人々と、ロビーの奥に身を寄せる人々。どちらがより安全か、より安全だとこの自分は決断するのか。もしかしたらこれが運命の分かれ道になるかもしれないという選択を、ひとは案外無意識のうちに連続して行っているものなのだろう。吹き抜けから見渡せるガラス張りの丸善2階や3階の店内で、2mほどの紐で吊られた水平に細長い照明の列がみな向きを揃えて盛大に揺れている。よく遊園地にあるヴァイキングのアトラクションを想い起こした。ロングシップは前後に揺られ、船首船尾は宙を行き交う。靴紐を締め直し、右肩に掛けていたバックを両肩で背負い直す。革手袋をはめ、眼鏡をかける。さあ、ビルを出ようか。
横断歩道を渡り、丸の内北口へ。東京駅丸の内口周辺はすべてがリニューアルされていくさなかにある。すでにオープンした新丸ビルや最後まで保存運動が続いた中央郵便局ビルの再開発に並んで、東京駅駅舎のドーム復元もその目玉事業の一つだが、おかげでトタン板に囲まれた臨時通路に遠回りを余儀なくなれ、しかも携帯電話を耳につける人々の周囲への不注意がひとの流れを阻害して歩きにくい。このとき、やたら携帯電話を手にする人々が多いことを、どうせ大揺れの感想でも述べ合っているのだろうくらいにしか思わなかった。とにかくわたしは歩くのです、さあさあ道をあけなさい。
駅の外側を北口から南方向へ。東京駅丸の内中央口には駅舎の皇室御用達スペースを囲う形でホテルや美術館などが併設されていて、地下のレストランが地上に掲示しているメニュー内の数千円のステーキ丼がいつも気になっていた。けれど今回はそんなことも脳裏をよぎらず南口へ、さらに南口からガード沿いを有楽町方面へとまっしぐらに歩く、歩く。丸の内南口に隣接する“はとバス”ステーション周辺ははとバスが数台止まっているゆえ全体的に黄色いのが常なのだが、いかにも運転手然とした白手袋に紺の背広姿のおじさんや旗を持ったバスガイド嬢が幾人もうろうろして、普段は閑散としたこの辺りもやや物々しい。
有楽町フォーラムを目前に左手へ折れ、JR線路をくぐって八重洲南口方面へ。次の目的地、八重洲ブックセンターに到着。やはり2階より上は一時封鎖。しかし書店員さんの内線電話を盗み聞きするに、6階から上はまだ危険だが、5階まではもうじき開放するとの由。いわゆる巨大書店としてはかつて長く全国一の地位を保ってきた老舗だけに、どう考えても周辺でもとびきり古そうなこのビルでその姿勢はなかなか冒険的だと内心で評価する。この店の客用エレベーターはなぜか4階から上しかないのだが、その不思議設計くらい冒険的な試みだ。
けれど時間も迫ってきたので1階の文学棚だけ軽く覗いて店を出る。数寄屋橋方面へ南下。東京駅周辺でも区画が整っていて大規模再開発の進む丸の内側に対し、八重洲側はごみごみした中小ビルが多くしかも揃ってみな古い。その差は約30分前の地震被害の差として歩道の端に明確に表れていて、なんと八重洲側では複数の場所で歩道のコンクリートとビルの礎石のあいだがひび割れていた。場所によっては高さ10cmの亀裂が横に長く伸びていて、え、そこまでひどかったのか、と少し驚く。しばらく亀裂を眺めていると、急に増え出した人通りのうち幾人かもそれに気づき、携帯で写真を撮りだす。写真を撮る彼らを撮るという思いつきを抑えつつ、歩行再開。このとき、銀座方向からのひとの出の増加に何となく不自然さを感じていたものの、その理由へ思考を巡らせるにはまだ至らず。映画の時間がそろそろ近づいてきた。
数寄屋橋近くまで来るとパトカーが一台、首都高のガード下を抜けて有楽町へと向かう一方通行の車道を塞ごうとしている。無音でサイレンを点滅させたまま、道の向きに対して真横になるようハンドルを切り返していく。黒の車体に大きく目立つ黄色の縁取りでPOLICEの文字。あ、そういえばずいぶん前から警視庁っていう表示から変わってたっけ、とか思う。数寄屋側では何も起きている様子はない。とすれば有楽町方向で何かが起きていることになる。あるいは起こることが予期されている。何か。
4時10分からの映画にはまだ少しだけ余裕がある。散策のルートを変更。パトカーの頭部を脇目に、ガード下をくぐって有楽町方面へと歩き始める。空気が冷たくなってきた。
映画は4時過ぎからなので、銀座まで歩くことを考えてもだいぶ間がある。都心のどこであれ本屋をはしごするのが時間潰しの基本ルートなのだが、初手で狂った。どうしようかとビルの吹き抜けロビーでしばらく人の流れを眺めていると、震動再来。高い天井から吊り下げられた照明や装飾の類が一斉に踊る。ロビーの人々、みな騒然。このとき群衆単位の動揺を目にしてようやく、体感はできないどこか遠方で予想外のおおごとが起きている可能性に気づく。あくまで可能性のレヴェル。まさかね。
再度、余震。広いロビーにたむろしていた集団が大きく二手に別れてゆく。足早にビルの外へと避難する人々と、ロビーの奥に身を寄せる人々。どちらがより安全か、より安全だとこの自分は決断するのか。もしかしたらこれが運命の分かれ道になるかもしれないという選択を、ひとは案外無意識のうちに連続して行っているものなのだろう。吹き抜けから見渡せるガラス張りの丸善2階や3階の店内で、2mほどの紐で吊られた水平に細長い照明の列がみな向きを揃えて盛大に揺れている。よく遊園地にあるヴァイキングのアトラクションを想い起こした。ロングシップは前後に揺られ、船首船尾は宙を行き交う。靴紐を締め直し、右肩に掛けていたバックを両肩で背負い直す。革手袋をはめ、眼鏡をかける。さあ、ビルを出ようか。
横断歩道を渡り、丸の内北口へ。東京駅丸の内口周辺はすべてがリニューアルされていくさなかにある。すでにオープンした新丸ビルや最後まで保存運動が続いた中央郵便局ビルの再開発に並んで、東京駅駅舎のドーム復元もその目玉事業の一つだが、おかげでトタン板に囲まれた臨時通路に遠回りを余儀なくなれ、しかも携帯電話を耳につける人々の周囲への不注意がひとの流れを阻害して歩きにくい。このとき、やたら携帯電話を手にする人々が多いことを、どうせ大揺れの感想でも述べ合っているのだろうくらいにしか思わなかった。とにかくわたしは歩くのです、さあさあ道をあけなさい。
駅の外側を北口から南方向へ。東京駅丸の内中央口には駅舎の皇室御用達スペースを囲う形でホテルや美術館などが併設されていて、地下のレストランが地上に掲示しているメニュー内の数千円のステーキ丼がいつも気になっていた。けれど今回はそんなことも脳裏をよぎらず南口へ、さらに南口からガード沿いを有楽町方面へとまっしぐらに歩く、歩く。丸の内南口に隣接する“はとバス”ステーション周辺ははとバスが数台止まっているゆえ全体的に黄色いのが常なのだが、いかにも運転手然とした白手袋に紺の背広姿のおじさんや旗を持ったバスガイド嬢が幾人もうろうろして、普段は閑散としたこの辺りもやや物々しい。
有楽町フォーラムを目前に左手へ折れ、JR線路をくぐって八重洲南口方面へ。次の目的地、八重洲ブックセンターに到着。やはり2階より上は一時封鎖。しかし書店員さんの内線電話を盗み聞きするに、6階から上はまだ危険だが、5階まではもうじき開放するとの由。いわゆる巨大書店としてはかつて長く全国一の地位を保ってきた老舗だけに、どう考えても周辺でもとびきり古そうなこのビルでその姿勢はなかなか冒険的だと内心で評価する。この店の客用エレベーターはなぜか4階から上しかないのだが、その不思議設計くらい冒険的な試みだ。
けれど時間も迫ってきたので1階の文学棚だけ軽く覗いて店を出る。数寄屋橋方面へ南下。東京駅周辺でも区画が整っていて大規模再開発の進む丸の内側に対し、八重洲側はごみごみした中小ビルが多くしかも揃ってみな古い。その差は約30分前の地震被害の差として歩道の端に明確に表れていて、なんと八重洲側では複数の場所で歩道のコンクリートとビルの礎石のあいだがひび割れていた。場所によっては高さ10cmの亀裂が横に長く伸びていて、え、そこまでひどかったのか、と少し驚く。しばらく亀裂を眺めていると、急に増え出した人通りのうち幾人かもそれに気づき、携帯で写真を撮りだす。写真を撮る彼らを撮るという思いつきを抑えつつ、歩行再開。このとき、銀座方向からのひとの出の増加に何となく不自然さを感じていたものの、その理由へ思考を巡らせるにはまだ至らず。映画の時間がそろそろ近づいてきた。
数寄屋橋近くまで来るとパトカーが一台、首都高のガード下を抜けて有楽町へと向かう一方通行の車道を塞ごうとしている。無音でサイレンを点滅させたまま、道の向きに対して真横になるようハンドルを切り返していく。黒の車体に大きく目立つ黄色の縁取りでPOLICEの文字。あ、そういえばずいぶん前から警視庁っていう表示から変わってたっけ、とか思う。数寄屋側では何も起きている様子はない。とすれば有楽町方向で何かが起きていることになる。あるいは起こることが予期されている。何か。
4時10分からの映画にはまだ少しだけ余裕がある。散策のルートを変更。パトカーの頭部を脇目に、ガード下をくぐって有楽町方面へと歩き始める。空気が冷たくなってきた。
2011.3.11メモランダム part1 <14時45分-15時 東京駅-丸の内>
2011年3月13日 陸沈
散歩日和の午後。シティバンクの新しい店舗が東京駅丸の内口に面した場所にあるのを知って、そこに寄りつつ銀座で映画を観て帰ろうという腹積もりで外出する。マフラーを持ち忘れたのに気づくが、そんなに遅くならないはずだしまあいいか、とあきらめる。けれど些細なその忘れ物が、妙に気になる。14時40分過ぎ、東京駅着。シティバンクの外貨取扱は15時までなので、まずは支店へ直行して用事を済ませようと考える。新しい支店は昔からあった大手町支店や銀座支店同様に上層客向け仕様になっていて、ドアマンのおじさんがきちんといて丁寧な挨拶とともに扉を開けてくれた。「ドアマンに扉を開けてもらう」のを待つ行為は、個人的にはどこかアジア的記憶に結びついてしまうので、顔濃いめのおじさんがインド人っぽく見えてきたけどふつうに日本人だった。ともあれ扉を抜け、受付のお兄さんに用事を話しかけたその瞬間、銀行内が揺れだした。おもてを見る。交差点を渡りかけたトラックが止まる。全面ガラス張りの窓が、重たい音を立て震え始める。
隣に立っていた裕福そうな白人の中年ビジネスマンは「なにごと!?」という感じで仁王立ちに天井を見つめたがすぐ中腰になり、中年太りにはあるまじき俊敏さで今にも動き出さんという素振りを見せる。銀行員のおねえさんが「外には出ない方がいい!」と叫んで白人ビジネスマンを一喝する。その声に顔を振り向けるとおねえさんと目が合ったが、そもそも英語だったし《あなたに言ったわけじゃないんです》的な微妙空間が生じる。この間2.5秒。
銀行員もお客さんも、ビルとともにしばらく揺られるに任せるしかなくて、視線だけはみな自然と外へ向いている。歩道とビルの間の縁石タイルが歩道に乗り出す形で揺れ動いている。ああこれが免震装置の威力かと感心する。NHKの散歩番組ブラタモリか何かで見たことがあるやつだが、ビル直下に敷き詰められた巨大バネ群の運動をこうもまざまざと実感する日が来るとは思わなかった。大張りガラスの窓から見える交差点周辺の車はみな止まり、運転席から降りるひともいる。丸の内北口の交差点でこの光景は非日常的というか、なにか映画っぽい。けれどこれは現実であって、15時までは数分しかなくて、ここで換金できないと手持ちの日本円がなくなってしまうのでちょっと困る。なので揺れながらも受付のお兄さんに手続き開始を要求せねばと目を向けるが、当然のことながら彼は本来の職務なりバンカーとして保つべき佇まいなどはそっちのけで外を見ている。「あれ、すごいですよ」と彼が指を斜め上方に向ける。目で追う。向かいの日本生命丸の内ビルに今いるビルが映っていて、全面ガラス張りの高層ビルの長身を弓なりにぐわんぐわん左右に曲げている。向かい合ったビルとビルがラジオ体操の音楽に合わせて身を反らせ合っている感じで、やっぱりどこか非現実。世界はどうなっちゃうんでしょうという実存的不安と、このまま15時過ぎたらお金どうなっちゃうんでしょうという卑近な困惑が入り雑じってわけわかめ。
その後いったん揺れは収まって銀行内も落ち着きを取り戻し、かがみ込んであぶら汗を浮かべ始めていた白人ビジネスマンも笑顔を取り戻す。恥ずかしげに「こんなの初めて!"#$」みたいなことをおねえさんに告白していたのがちょっとかわいい。わざわざ接客用の個室に招かれるのが申し訳ないくらい少額の換金をしてもらう。急いでサインしたら筆致が乱れて書き直しチェックをさせられた。外に出るとき再び扉を開けてくれたドアマンのおじさんが向けてきた真摯な視線の内側には、巨大な揺れをともにした共闘意識すら感じとれた。気のせいかもしれない。
横断歩道を渡ってOAZOの丸善へ向かう。このときわたしは地震の規模も知らず、このあと規格外の一日を体験する羽目になることもまだ知らなかった。
隣に立っていた裕福そうな白人の中年ビジネスマンは「なにごと!?」という感じで仁王立ちに天井を見つめたがすぐ中腰になり、中年太りにはあるまじき俊敏さで今にも動き出さんという素振りを見せる。銀行員のおねえさんが「外には出ない方がいい!」と叫んで白人ビジネスマンを一喝する。その声に顔を振り向けるとおねえさんと目が合ったが、そもそも英語だったし《あなたに言ったわけじゃないんです》的な微妙空間が生じる。この間2.5秒。
銀行員もお客さんも、ビルとともにしばらく揺られるに任せるしかなくて、視線だけはみな自然と外へ向いている。歩道とビルの間の縁石タイルが歩道に乗り出す形で揺れ動いている。ああこれが免震装置の威力かと感心する。NHKの散歩番組ブラタモリか何かで見たことがあるやつだが、ビル直下に敷き詰められた巨大バネ群の運動をこうもまざまざと実感する日が来るとは思わなかった。大張りガラスの窓から見える交差点周辺の車はみな止まり、運転席から降りるひともいる。丸の内北口の交差点でこの光景は非日常的というか、なにか映画っぽい。けれどこれは現実であって、15時までは数分しかなくて、ここで換金できないと手持ちの日本円がなくなってしまうのでちょっと困る。なので揺れながらも受付のお兄さんに手続き開始を要求せねばと目を向けるが、当然のことながら彼は本来の職務なりバンカーとして保つべき佇まいなどはそっちのけで外を見ている。「あれ、すごいですよ」と彼が指を斜め上方に向ける。目で追う。向かいの日本生命丸の内ビルに今いるビルが映っていて、全面ガラス張りの高層ビルの長身を弓なりにぐわんぐわん左右に曲げている。向かい合ったビルとビルがラジオ体操の音楽に合わせて身を反らせ合っている感じで、やっぱりどこか非現実。世界はどうなっちゃうんでしょうという実存的不安と、このまま15時過ぎたらお金どうなっちゃうんでしょうという卑近な困惑が入り雑じってわけわかめ。
その後いったん揺れは収まって銀行内も落ち着きを取り戻し、かがみ込んであぶら汗を浮かべ始めていた白人ビジネスマンも笑顔を取り戻す。恥ずかしげに「こんなの初めて!"#$」みたいなことをおねえさんに告白していたのがちょっとかわいい。わざわざ接客用の個室に招かれるのが申し訳ないくらい少額の換金をしてもらう。急いでサインしたら筆致が乱れて書き直しチェックをさせられた。外に出るとき再び扉を開けてくれたドアマンのおじさんが向けてきた真摯な視線の内側には、巨大な揺れをともにした共闘意識すら感じとれた。気のせいかもしれない。
横断歩道を渡ってOAZOの丸善へ向かう。このときわたしは地震の規模も知らず、このあと規格外の一日を体験する羽目になることもまだ知らなかった。
カダフィ大佐の息子による漫才 アルジャジーラにて放映中
2011年2月21日 陸沈liveで中継してます。
http://english.aljazeera.net/watch_now/
滅多にお目にかかれない愚か者演説で、ほとんどギャグの域に達してるので英語わかるひとにはぜひおすすめです。
独裁者の家族はまあなんていうか、精神的に成長の契機を奪われちゃってるのかな。その意味ではかわいそう。
※追記:
興味のあるひとならご存知の通り、リビアは歴史・文化的に大きく3地域に分かれているんですね。DOLプレイヤーにはおなじみのベンガジとトリポリ、この2都市の名はこの1週間ほどたびたび報道に載っていましたが、それぞれがこの3地域のうち2地域の中核都市です。体制側としては、今回の民衆による運動を「東部地域の分裂運動」だとして非難しています。エジプトのようには行かないとか、石油を基盤にした国家運営に傷がつくとか、まあいろいろ言ってました。
アデンやアルジェも報道には頻出しています。これに対して国内のテレビ・新聞は小沢がどうの自民党がどうのと実に終わってる感満載。こういうときに奮起しないでなんのためのメディアなのかと。ほぼ同時刻のNHKニュース。「リビアでは国営放送が反政府運動については一切報じていません(キリッ」 う、うん…。
現在進行中のアラブ革命。Facebookとイスラムばかりが要素として強調されてますが、私見では一番大きな要因は“アメリカの影響力低下”に他なりません。多くの独裁政権が長期化することで、実は最も恩恵を受けてきたのは皮肉な話アメリカなんですね。もし全世界が民主化・自由経済化したら、アメリカの相対的地位低下は誰の目にも明らかだからです。したがってこの流れはなにも中東に限ったことではなく、他のアフリカ・アジア地域やカリブ・南米などへ広がる可能性は高いと思います。
たとえばハイチでは前代や前前代の独裁者一族が亡命先から返り咲こうとする言動を始めているようです。インドネシア島嶼部や中国極西部なども騒がしくなってくるでしょう。中国やロシアの政府にとって尖閣と千島四島の問題で唯一重要なのは、それが自分たちの統治を揺るがし得る要素になるか否か、です。そこを最も恐れていて、それに比べれば領土的野心など二義的なものに過ぎません。ですからこれらは現下の動向と、実はじかに連関しているんですね。つまり問題の評価軸が日本の尺度とは根本的に異なっている。民主党の振る舞いはあまりに稚拙過ぎたと思います。そこらへんの連関がなぜテレビや新聞で論じられないのか、もしかしたら今はまだ下り坂の入り口に過ぎないのかもしれないと思うのは、こういう疑問に駆られたときだったりします。
http://english.aljazeera.net/watch_now/
滅多にお目にかかれない愚か者演説で、ほとんどギャグの域に達してるので英語わかるひとにはぜひおすすめです。
独裁者の家族はまあなんていうか、精神的に成長の契機を奪われちゃってるのかな。その意味ではかわいそう。
※追記:
興味のあるひとならご存知の通り、リビアは歴史・文化的に大きく3地域に分かれているんですね。DOLプレイヤーにはおなじみのベンガジとトリポリ、この2都市の名はこの1週間ほどたびたび報道に載っていましたが、それぞれがこの3地域のうち2地域の中核都市です。体制側としては、今回の民衆による運動を「東部地域の分裂運動」だとして非難しています。エジプトのようには行かないとか、石油を基盤にした国家運営に傷がつくとか、まあいろいろ言ってました。
アデンやアルジェも報道には頻出しています。これに対して国内のテレビ・新聞は小沢がどうの自民党がどうのと実に終わってる感満載。こういうときに奮起しないでなんのためのメディアなのかと。ほぼ同時刻のNHKニュース。「リビアでは国営放送が反政府運動については一切報じていません(キリッ」 う、うん…。
現在進行中のアラブ革命。Facebookとイスラムばかりが要素として強調されてますが、私見では一番大きな要因は“アメリカの影響力低下”に他なりません。多くの独裁政権が長期化することで、実は最も恩恵を受けてきたのは皮肉な話アメリカなんですね。もし全世界が民主化・自由経済化したら、アメリカの相対的地位低下は誰の目にも明らかだからです。したがってこの流れはなにも中東に限ったことではなく、他のアフリカ・アジア地域やカリブ・南米などへ広がる可能性は高いと思います。
たとえばハイチでは前代や前前代の独裁者一族が亡命先から返り咲こうとする言動を始めているようです。インドネシア島嶼部や中国極西部なども騒がしくなってくるでしょう。中国やロシアの政府にとって尖閣と千島四島の問題で唯一重要なのは、それが自分たちの統治を揺るがし得る要素になるか否か、です。そこを最も恐れていて、それに比べれば領土的野心など二義的なものに過ぎません。ですからこれらは現下の動向と、実はじかに連関しているんですね。つまり問題の評価軸が日本の尺度とは根本的に異なっている。民主党の振る舞いはあまりに稚拙過ぎたと思います。そこらへんの連関がなぜテレビや新聞で論じられないのか、もしかしたら今はまだ下り坂の入り口に過ぎないのかもしれないと思うのは、こういう疑問に駆られたときだったりします。
毎日を暮らしていくなかで、風化していき、埋もれていってしまうものも多いのだけど、すこし目を凝らすなら良いことも同じようにたくさん起きている。目のまえの出来事ばかりに追われているうちは、ともすれば忘れそうになりがちなこの世界のリアルはだから、いつも視界の端にあると思うくらいがたぶんいい。
さいきん、フェイスブックに初めて登録してみたら驚いた。十年は会っていないような昔の友だちや知り合いが、芋づる式にゴロゴロ出てくる。昔つき合っていて、その後音信不通になったひとも何人か出てきたりして、半分くらいは結婚してた。もう何も期待してないせいもあるのだろうけど、あんがい素直に祝福の気分にひたれるものだ。そんなことより何より一番驚いたのは、ああこれは凄いなとひそかに感心していたひとたちの大半が、仕事や生活の拠点を海外に移していたということだ。ほんのりとした、やられた感。なるほどそうきたか、そうきましたかおっかさんという感じ。
ほの暗いるつぼのなかにあるとして、そこに何を見いだすかは結局ひとそれぞれだ。
おとのうてあらわれ映るもの、きみは。
っていうのが略奪後にのこすsayの定番だったんだけど、そもそもうちの名前から中華の業者さんを連想する人なんて、じきにプレイ6年目に入る古株さんでもさすがにもういなさげだよね。いるのかな。日本語の不自由な両親のキャラを最後に見たのはもう4年は前かもしれない。けっきょく一度も襲えなかった。いや、一度くらいはあったかな。まだようやくガレーに乗り出したころ、なぜか胡椒くれたのを覚えてる。
せっかくだしカナリア沖に出てみるかーっていろんな作業の合間にちまちま沖へ出てみたけれど、むかし追いつけた風向きと船種でも一瞬にして商船が水平線のかなたに消えるです。びっくりだね。リニアモーターカーにうっかり遭遇しちゃった甲州街道のお侍さんな気分だよ。でもそれならそれで遊べちゃう子だから遠洋ソロ海賊とかしてたんだよね、とかあらためて思い出しつつ蝦夷島一周するところまでやってみた。東アジア安全海域とか、安心すぎて揚子江さかのぼり始めたら後ろからガレアスっぽいの来た。ホラーホラー。
あとはなんだ。けさは諸般の事情で朝からちょっと酔っ払ってるんである。さっきFEZやったら敵軍にレムオンさんがいていじめられた。なんだあの強さは。っていうかなんだこの弱さは。まあいいや。なにがどうしてこうなったのかよくわかんないけど、太古のむかしからきっとみんなそんな感じだったんだろうし更新しちゃう。してしまうのであった。
せっかくだしカナリア沖に出てみるかーっていろんな作業の合間にちまちま沖へ出てみたけれど、むかし追いつけた風向きと船種でも一瞬にして商船が水平線のかなたに消えるです。びっくりだね。リニアモーターカーにうっかり遭遇しちゃった甲州街道のお侍さんな気分だよ。でもそれならそれで遊べちゃう子だから遠洋ソロ海賊とかしてたんだよね、とかあらためて思い出しつつ蝦夷島一周するところまでやってみた。東アジア安全海域とか、安心すぎて揚子江さかのぼり始めたら後ろからガレアスっぽいの来た。ホラーホラー。
あとはなんだ。けさは諸般の事情で朝からちょっと酔っ払ってるんである。さっきFEZやったら敵軍にレムオンさんがいていじめられた。なんだあの強さは。っていうかなんだこの弱さは。まあいいや。なにがどうしてこうなったのかよくわかんないけど、太古のむかしからきっとみんなそんな感じだったんだろうし更新しちゃう。してしまうのであった。
ぼんやりとした良さの意味
2009年6月13日 常在戦場 コメント (2)
今年4回目の課金中です。とはいえ諸事情により、海に出て活動するのは週1,2回くらい。
▼アズレージョ紋様のゲーム内的価値について
現在開催中のLiveイベント“オポルト漁師まつり ~Festival de Pescador~”、もはや新規の試みには付き物の運営サイドによる読み違えもありましたが、それなりに楽しめているひとは多いようですね。今回はこのイベントを巡って書こうと思い立ちました。まず取り上げたいのは公式HP内イベントページの意匠について。
公式HP: http://www.gamecity.ne.jp/dol/live_event/090602.htm
‘大航海時代Online’のゲーム内では、地理歴史や異国文化にとても精通しているプレイヤーによく出会います。上記イベント告知の見出しやアイコンに使われている意匠をみて‘おっ!’と思っただろうそうした方々には言わずもがなの話になりますが、これ、イベントの舞台であるポルトガルの文化史を語るうえでは外すことのできない“アズレージョ”技法に典型的な文様なんですね。[右上画像]
もちろんアイコンや背景を言及内容に関連させてデザインするというのはウェブ一般においてよくある話だし、‘大航海時代Online’の過去のイベントでも例えばヴァレンタインのときは薔薇やハートマーク、ハロウィンであればかぼちゃのアイコンが登場するといった工夫はありました。しかし今回の場合、‘魚’や‘釣り具’のアイコンではなくアズレージョ模様が採用されているところに新鮮さがあります。この発想はアイコンに各国の紋章等を採用するのともまた違ったセンスの存在を窺わせ、大袈裟な言い方をすれば個人的にイベント内容よりもこのデザインを目にして、‘このゲームまだまだ行けそうかも’と可能性を感じました。
▼エラーの真髄
わたしは昨今の運営サイドが見せる全体的なスタンスに対してはかなり不可解な思いを抱くようになったプレイヤーの一人なのですが、その不可解さを根拠にイベントの不備を具体的に並べたてるのは今さら不毛なので省略します。運営にユーザー側の不満を吸い上げる機構が働いているとすれば、今回の失策に伴う批判の声も未来の類似イベントにおける改善の素材としていずれは消費されてゆくことでしょう。
ただ‘PS3で始めた初心者も主体となって楽しめるイベント’という企図が前面に出過ぎ、普段はプレイスタイルが異なるため一緒に遊べない商会員やフレと一緒にできるイベントが何であれ欲しい、指示通りに移動して周るお使いクエストではなくできれば戦闘も絡まず他プレイヤーと協働する時限的なイベントがしたい、などといった既存プレイヤーの幾らかが日々蓄積しているだろう潜在的な需要の総量を読み違えていたとすれば、そこは大いに熟考されて良いことだろうと思います。また運営サイドが、プレイヤー側から‘そのように見える’素振りを毎度繰り返していることの意図がいまだわかりません。(言うまでもなく私見です。)
▼ぼんやりとした良さの意味
現在の運営スタンスへの疑問とは対照的に、ゲーム内では今でも時折、‘この設定はすごいな’と感心させられる場面があります。それはインド圏の交易所主人の脇に置かれたさりげない道具であったり、東南アジアのNPCが発するちょっとしたひとことや、洋上グラフィックにおけるジェロニモス修道院のかわいさ(リスボン港を表すデフォルメされた教会の3Dグラフィックです)であったりするのだけれど、わたしのようにわざわざ意識化/言語化させずとも、それらを‘大航海時代Online’がもつ魅力の重要な要素として楽しんでいるプレイヤーはきっと多いはずです。
これらが、例えばゲーム内に登場する各文化の多彩な衣装などのように、誰から見てもこのゲームの“売り”として明確に認識されうる要素では必ずしもない、というところがこの文脈ではポイントです。こうしたあたりを以下長々と書き連ねるのも疲れるので、類似言及のある叔父貴のブログ記事を紹介してそれに代えます。目線としてはもっとマニアックになりますが。
浮上する天蓋: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-48.html
言い方を真似れば、今回の“オポルト漁師まつり”についてのブログをしばらく見てまわった限りではアズレージョへの言及は見当たらなかったけれど、この点を巡ってユーザーサイドからの明記された評価が存在するのは大事だろうと思ったので、ひさびさに更新してみました、という感じになるでしょうか。そのアイコンの向こう側に連綿と続いてきたリアルの歴史文化の香りを漂わせることができるのは、‘大航海時代Online’が他のネットゲームに対してもつ強力な武器の一つなんですよね。仮に公式HPのデザイナーにとっては些細な思いつきに過ぎないとしても、そこがただのハート型アイコンとは自ずと違ってくるわけです。
▼おまけ
画像は一つ目がアズレージョ紋様のアイコン、二つ目が知り合いの体験版プレイヤーのかたへの街頭インタヴュー。一行目はわたしの発言です。参考までにwikipedia内アズレージョ紋様の解説ページを↓ やけに詳しいです。[要コピペ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7
コメントが付いてないのにコメント数だけ伸びる現象、何かと思ったらDiary Note全般に起きているようですね。すぐに修正されないところがいかにもDiary Noteらしくて素敵です。最近はネタも下書きもあるのに、なかなか記事更新までやり切る余裕が生まれません。こうしてボツになったテキストが過去大量にあるのはさても恐ろしきことなりけり。
▼アズレージョ紋様のゲーム内的価値について
現在開催中のLiveイベント“オポルト漁師まつり ~Festival de Pescador~”、もはや新規の試みには付き物の運営サイドによる読み違えもありましたが、それなりに楽しめているひとは多いようですね。今回はこのイベントを巡って書こうと思い立ちました。まず取り上げたいのは公式HP内イベントページの意匠について。
公式HP: http://www.gamecity.ne.jp/dol/live_event/090602.htm
‘大航海時代Online’のゲーム内では、地理歴史や異国文化にとても精通しているプレイヤーによく出会います。上記イベント告知の見出しやアイコンに使われている意匠をみて‘おっ!’と思っただろうそうした方々には言わずもがなの話になりますが、これ、イベントの舞台であるポルトガルの文化史を語るうえでは外すことのできない“アズレージョ”技法に典型的な文様なんですね。[右上画像]
もちろんアイコンや背景を言及内容に関連させてデザインするというのはウェブ一般においてよくある話だし、‘大航海時代Online’の過去のイベントでも例えばヴァレンタインのときは薔薇やハートマーク、ハロウィンであればかぼちゃのアイコンが登場するといった工夫はありました。しかし今回の場合、‘魚’や‘釣り具’のアイコンではなくアズレージョ模様が採用されているところに新鮮さがあります。この発想はアイコンに各国の紋章等を採用するのともまた違ったセンスの存在を窺わせ、大袈裟な言い方をすれば個人的にイベント内容よりもこのデザインを目にして、‘このゲームまだまだ行けそうかも’と可能性を感じました。
▼エラーの真髄
わたしは昨今の運営サイドが見せる全体的なスタンスに対してはかなり不可解な思いを抱くようになったプレイヤーの一人なのですが、その不可解さを根拠にイベントの不備を具体的に並べたてるのは今さら不毛なので省略します。運営にユーザー側の不満を吸い上げる機構が働いているとすれば、今回の失策に伴う批判の声も未来の類似イベントにおける改善の素材としていずれは消費されてゆくことでしょう。
ただ‘PS3で始めた初心者も主体となって楽しめるイベント’という企図が前面に出過ぎ、普段はプレイスタイルが異なるため一緒に遊べない商会員やフレと一緒にできるイベントが何であれ欲しい、指示通りに移動して周るお使いクエストではなくできれば戦闘も絡まず他プレイヤーと協働する時限的なイベントがしたい、などといった既存プレイヤーの幾らかが日々蓄積しているだろう潜在的な需要の総量を読み違えていたとすれば、そこは大いに熟考されて良いことだろうと思います。また運営サイドが、プレイヤー側から‘そのように見える’素振りを毎度繰り返していることの意図がいまだわかりません。(言うまでもなく私見です。)
▼ぼんやりとした良さの意味
現在の運営スタンスへの疑問とは対照的に、ゲーム内では今でも時折、‘この設定はすごいな’と感心させられる場面があります。それはインド圏の交易所主人の脇に置かれたさりげない道具であったり、東南アジアのNPCが発するちょっとしたひとことや、洋上グラフィックにおけるジェロニモス修道院のかわいさ(リスボン港を表すデフォルメされた教会の3Dグラフィックです)であったりするのだけれど、わたしのようにわざわざ意識化/言語化させずとも、それらを‘大航海時代Online’がもつ魅力の重要な要素として楽しんでいるプレイヤーはきっと多いはずです。
これらが、例えばゲーム内に登場する各文化の多彩な衣装などのように、誰から見てもこのゲームの“売り”として明確に認識されうる要素では必ずしもない、というところがこの文脈ではポイントです。こうしたあたりを以下長々と書き連ねるのも疲れるので、類似言及のある叔父貴のブログ記事を紹介してそれに代えます。目線としてはもっとマニアックになりますが。
浮上する天蓋: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-48.html
言い方を真似れば、今回の“オポルト漁師まつり”についてのブログをしばらく見てまわった限りではアズレージョへの言及は見当たらなかったけれど、この点を巡ってユーザーサイドからの明記された評価が存在するのは大事だろうと思ったので、ひさびさに更新してみました、という感じになるでしょうか。そのアイコンの向こう側に連綿と続いてきたリアルの歴史文化の香りを漂わせることができるのは、‘大航海時代Online’が他のネットゲームに対してもつ強力な武器の一つなんですよね。仮に公式HPのデザイナーにとっては些細な思いつきに過ぎないとしても、そこがただのハート型アイコンとは自ずと違ってくるわけです。
▼おまけ
画像は一つ目がアズレージョ紋様のアイコン、二つ目が知り合いの体験版プレイヤーのかたへの街頭インタヴュー。一行目はわたしの発言です。参考までにwikipedia内アズレージョ紋様の解説ページを↓ やけに詳しいです。[要コピペ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7
コメントが付いてないのにコメント数だけ伸びる現象、何かと思ったらDiary Note全般に起きているようですね。すぐに修正されないところがいかにもDiary Noteらしくて素敵です。最近はネタも下書きもあるのに、なかなか記事更新までやり切る余裕が生まれません。こうしてボツになったテキストが過去大量にあるのはさても恐ろしきことなりけり。
▼新居イスタンブール
オスマン帝国へ移籍してひと月がすでに経ちました。思っていたより悪くない、というのが現在の印象です。今回は個人の視点から、移籍初月の感想をまとめてみます。
【デメリット】 まず実装前から予想されていたデメリットについて
・首都の場所: これまで共有倉庫も商館の出し入れもセビリアだったので、アパルタメントだけが遥かイスタンブールに移転したのはやはり手間ですね。そもそもあまり戻らないので普段は良いのだけど、大海戦時は携行物を大量に入れ替えるのでセビリア―イスタン間の移動もしくは回航費用が単純にコストとして増えました。
・入港賄賂: 基本的に賞金首の状態は今後も継続しそうなので、欧州各国の本拠地と開拓地への入港時には賄賂支払いがデフォルトになりました。これがキツければ商会移籍も検討する気だったのですが、このひと月の間セビリアに戻るたび商館の売上がだいたい10M入ったため、出向所役人に要求される1回0.5Mの賄賂は気にならず。
むしろこれを忘れて、カリブの各開拓地で不意に賄賂を要求されるのが予想外のデメリットでした。補給はできるので些細なことだし、一時的な慣れの問題になりますね。
・名声の大幅減少: 移籍前に欧州各国への亡命巡りをやったこともあり、名声値は3年前のそれを軽く下回るほど減少しました。冒険名声など0になってしまったので、今後冒険クエストをやる気になった際には大きなコストになるかも。現在のプレイスタイルへの影響はなし。
・悪名の加算: 移籍によって無条件に8000の悪名が加算されました。ふつうこれはデメリットになるはずですが、わたしの場合はこれを機会に戦利品を換金したのでお得イベントに。(対人上納品を使用されると獲得できる戦利品は、悪名が高いほど換金率が良くなります。)
【メリット】 次は事前に告知されていた各種メリットについて
・スエズ運河: カイロ―スエズ間の運河使用料/時間は、オスマン船籍の場合およそ150k/10分。もともと定期船の乗り換えがものすごく苦手で、ながら作業の長距離航海が苦にならない身としては、これは思いのほか便利に感じられました。アパルタメントがイスタンブールに移ったため、事前の予想以上によく使っています。
・変装不要/特別回航/専用陸路: オスマン領地・同盟港への変装が不要なのは、アイテム枠的に少し嬉しいかも。拠点回航とは別に使用できるイスタンブール回航、バスラ―ヤッファ間の陸路ともにまだ試していませんが、ひとによっては使える利点になりそうですね。
・ハイレディンの助言/援軍: アルジェでもらえるハイレディンの助言はパターンがいくつもあって、NPCとの会話としては新鮮で面白かったです。彼の船が登場するという援軍アイテムはまだ使ったことがありません。何かのイベント時にでも使うと、艦隊メンバーへのささやかなサービスにはなるかなw
【まとめ】
もしかしたらプレイ環境がけっこう変わるかもという期待もしくは恐れを抱いての移籍でしたが、思ったほど変わらず。悪名さえ落とせば欧州各国への敵対度固定でも賄賂は要求されないので、オスマン移籍は特に冒険家スタイルをとるプレイヤーにとって事前に予想されていた以上にメリットの大きな選択肢になっていると言えそうです。
画像はいずれも移籍時前後のもの。爵位が“藩主”って慣れない語感ですね。一つ下のかたは“知事”らしく。移籍によるPK(対人海賊)プレイ周辺の変化については、それなりにありました。あと初めて港の投資ランカーにもなってみたり。長くなったのでこれらについては機会をあらためます。史実のハイレディンに興味のあるかたは下記URLをどうぞ。ではまた再見~
ハイレディンという栄光: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-76.html
オスマン帝国へ移籍してひと月がすでに経ちました。思っていたより悪くない、というのが現在の印象です。今回は個人の視点から、移籍初月の感想をまとめてみます。
【デメリット】 まず実装前から予想されていたデメリットについて
・首都の場所: これまで共有倉庫も商館の出し入れもセビリアだったので、アパルタメントだけが遥かイスタンブールに移転したのはやはり手間ですね。そもそもあまり戻らないので普段は良いのだけど、大海戦時は携行物を大量に入れ替えるのでセビリア―イスタン間の移動もしくは回航費用が単純にコストとして増えました。
・入港賄賂: 基本的に賞金首の状態は今後も継続しそうなので、欧州各国の本拠地と開拓地への入港時には賄賂支払いがデフォルトになりました。これがキツければ商会移籍も検討する気だったのですが、このひと月の間セビリアに戻るたび商館の売上がだいたい10M入ったため、出向所役人に要求される1回0.5Mの賄賂は気にならず。
むしろこれを忘れて、カリブの各開拓地で不意に賄賂を要求されるのが予想外のデメリットでした。補給はできるので些細なことだし、一時的な慣れの問題になりますね。
・名声の大幅減少: 移籍前に欧州各国への亡命巡りをやったこともあり、名声値は3年前のそれを軽く下回るほど減少しました。冒険名声など0になってしまったので、今後冒険クエストをやる気になった際には大きなコストになるかも。現在のプレイスタイルへの影響はなし。
・悪名の加算: 移籍によって無条件に8000の悪名が加算されました。ふつうこれはデメリットになるはずですが、わたしの場合はこれを機会に戦利品を換金したのでお得イベントに。(対人上納品を使用されると獲得できる戦利品は、悪名が高いほど換金率が良くなります。)
【メリット】 次は事前に告知されていた各種メリットについて
・スエズ運河: カイロ―スエズ間の運河使用料/時間は、オスマン船籍の場合およそ150k/10分。もともと定期船の乗り換えがものすごく苦手で、ながら作業の長距離航海が苦にならない身としては、これは思いのほか便利に感じられました。アパルタメントがイスタンブールに移ったため、事前の予想以上によく使っています。
・変装不要/特別回航/専用陸路: オスマン領地・同盟港への変装が不要なのは、アイテム枠的に少し嬉しいかも。拠点回航とは別に使用できるイスタンブール回航、バスラ―ヤッファ間の陸路ともにまだ試していませんが、ひとによっては使える利点になりそうですね。
・ハイレディンの助言/援軍: アルジェでもらえるハイレディンの助言はパターンがいくつもあって、NPCとの会話としては新鮮で面白かったです。彼の船が登場するという援軍アイテムはまだ使ったことがありません。何かのイベント時にでも使うと、艦隊メンバーへのささやかなサービスにはなるかなw
【まとめ】
もしかしたらプレイ環境がけっこう変わるかもという期待もしくは恐れを抱いての移籍でしたが、思ったほど変わらず。悪名さえ落とせば欧州各国への敵対度固定でも賄賂は要求されないので、オスマン移籍は特に冒険家スタイルをとるプレイヤーにとって事前に予想されていた以上にメリットの大きな選択肢になっていると言えそうです。
画像はいずれも移籍時前後のもの。爵位が“藩主”って慣れない語感ですね。一つ下のかたは“知事”らしく。移籍によるPK(対人海賊)プレイ周辺の変化については、それなりにありました。あと初めて港の投資ランカーにもなってみたり。長くなったのでこれらについては機会をあらためます。史実のハイレディンに興味のあるかたは下記URLをどうぞ。ではまた再見~
ハイレディンという栄光: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-76.html
魔坑にて 弐: ネット人格にプライドはありうるか!?
2009年3月12日 ネットゲームの魔坑にて コメント (26)
先月の記事「転売バザーの生態調査!」は、結果的にコメント欄こそが記事本体というような展開を見せました。良い機会なので、新しく『ネットゲームの魔坑にて』と題した記事シリーズを立てておきます。
今回は、先月の記事「転売バザーの~」に付いたコメント36番目の全文転載から始めます。以下転載部分を囲みにて。HN“既に遅いですが。”さんより。
転載以上。話が色々盛り込まれているので、まず気になる文節ごとにレスを。
> #タガが外れているから痛い人が目立ちますが。
その‘タガ’のかなりの部分が共同幻想に基づいているんですよね。けれども、ネットゲーム内部であれば自身の‘タガが外せる’と判断してしまえる発想自体も実は丸ごと、当の共同幻想に規定されているわけです。つまり、‘ゲーム内だからという理由でタガを外した行為にでる自分’を、リアルの自分は自覚的であれ無自覚にであれ受け入れざるを得ない。けれどもそうした‘お約束’を知ってさえいれば、ゲーム内だからと‘タガ’を外してしまうのが本当は自分を貶める行為であることに気づけます。これは匿名掲示板などについても言えることです。
ポイントは、そこで貶められるものが「他者関係のなかで維持確認される自尊心」ではなく、「自分の自分自身へ向けたセルフリスペクト」であるということですね。両者の違いが分からないのは端的に幼稚さの証ですから、‘そのように見える’言動をするひとに対して周囲のプレイヤーはごく常識的に‘痛い’と感じてしまうわけです。
たとえば匿名による短絡思考の書き捨てや他者への中傷行為が、よく言われるように自身を安全圏に置いた行為ではありえず、実は自意識の基底レヴェルで深刻な自傷被害をもたらしていることに、やっている本人たちは無論気づきません。気づかないからこそどんな悪言を吐いても自分は傷つかないと誤認できるのですが、しかしそこで損なわれた、あるいは未成熟ゆえあらかじめ脆弱な自己評価こそが、その後の各人の実像をじかに形成していくという現実には抗いようがありません。
ちなみに、こうしてたかがゲームを巡って長文を巡らせるgoodbyeの身振りなどもまた、別の意味でごく常識的に‘痛い’ひとに見えているはずです。だとすれば、そんな人間のつらねる言葉を延々とここまで読み続けてきたあなた、コメントをいただいたHN“既に遅いですが。”さんではなく、コメントは書き込まずともウォッチャー感覚で面白がり今モニターに向かっているそこのあなた、もまた当然のことながら、まぎれもなく同様に、‘痛い’です。この局面では匿名性の有無が無意味化するのも、自らの行為に対しセルフリスペクトを保てているか否かこそが分水嶺になるからです。ならばもう、一緒に芝生を育ててしまうのもありですね。
> ・なぜPKをやっているのか。
そこでやや小難しい言い方のまま続けてしまいますが、ネットゲーム内部に侵入しているその共同幻想の‘輪郭’をより見極めたいというのがPK(Player Killer:他のプレイヤーを直接攻撃するひと)のスタイルをとる動機の前提にあるような気がします。このゲームを始めた初期のわたしは、「PKなんて超迷惑なだけじゃん。色付きの人らって、ちょっと頭おかしいんじゃない?」くらいに思う種のひとたちに、心情的にはむしろ近かった気がします。ただ“なぜそう思うのか”に時を待たず興味が移ったことは、いま思えばPKへの不快さを不快さのまま抱え続けるプレイヤーとの分岐点だったのかもしれません。これに続けて、↓
> ・なぜゲーム内の自らのキャラ名を晒してブログを書くのか。
キャラ名によるプレイヤーブログの存在を始めて知ったときも、「なんなんだこのひとたち、たかがゲームに入れ込み過ぎてちょっちキモイ」くらいに感じたものです。ブログというのはもっと日常や思考生活を広範に扱うものという先入観があったんですね。だからとりあえず自分でもやってみた、というのが理由の一つ。いざ始めてみると、内面的にこれはこれで継続するに足る一本の芯が通ったというのがもう一つ。
つまり当ブログの存在は3年前のわたしにとってすら、キモイ。いはんや世人にとりてをや。
> ・転売行為の是非はともかく、行為は悪質だと感じてらっしゃいますよね?
あるひとの抱えもつ‘善意’は、他者によっては通用しないケースが大いにあり得るという点で極めて主観的なものですよね。鄭和さんがコメントでそれを‘信仰’と表現された通り、その基盤には祈りにも近い深く個人的な思惟、もしくは他者に対する安易でイノセントな思い込みがあります。そしてこの基準に照らせば悪質と判断するしかないというニュアンスで、転売一般にではなく個別特定的に片桐さん(≒目の前で転売を始めてしまうスタイル)に対して、確かにわたしは悪質だと感じています。もっともそれ自体は記事中から読み取れるとしても話を俎上にのせるためのブースターに過ぎず、その行為を行為者本人が悪質と考えてやっているかどうかという別の問題こそが、個人的には関心の焦点だったわけです。
ただしこのことも、いわゆる‘中のひと’の人間性と短絡できるような直接関係はないと考えています。ここから以下、各論的なレスを一度離れます。
▼画像と予告
というわけでここからが本論部なのですが、すでに長過ぎるので一旦切って今回は終わります。続きはまたいつか。右上画像は、オスマン帝国との‘契約’前に終えたイスパニアイベントと、各国亡命行脚中の一光景です。鄭和さんとネモッティさんの画像は事前了承なしの掲載です。鄭和さんはこの記事でも再度お名前を拝借してますのでご登場いただきました。ネモさんは長く敵対私掠の間柄でしたが、実はそれ以前の低レベルの頃からフレだったりします。ないと思いますが万一画像掲載に問題あれば削除するのでお知らせを。
また今回の新記事シリーズ開始にあわせ先月の記事を事後的に「魔坑にて 壱:転売バザーの生態調査!」と改めます。記事シリーズ検索は左欄下方(テーマ別一覧)にて。
この記事シリーズは、読み手のかたからの反応によって後続するテーマを変えていきます。「壱」にいただいた反応から、見切り発車によるそうした方法もアリなのに気づきました。こうした経緯のため、「壱」へのコメントも、今後は当記事シリーズの最新記事にいただけると流れ的にまとめやすく、助かります。
忌憚ないコメントがいただければ、その流れから見えてくる新たなテーマもありそうだと期待します。ぜひ思うところをお気楽にコメントお寄せください。よろしくです。
今回は、先月の記事「転売バザーの~」に付いたコメント36番目の全文転載から始めます。以下転載部分を囲みにて。HN“既に遅いですが。”さんより。
初めて拝見しましたが、君たちまとめて面白いw
言いたいことがあるなら言えば良いし、やりたい事があるならやれば良いと思うんだ。好きなように自由にね。ただ他人に迷惑をかけている人は、バッシングされる事は覚悟しないと。
後、引っ掛かったのが・・・
>読み手のほうで勝手に読み取った掲載意図を頑なに信じ込んで、疑いもなくこちらにぶつけてくる
これ現実社会でも多いですよね。
逆を言えばDOLって見事に現実社会の縮図な気もします。
#タガが外れているから痛い人が目立ちますが。
本来全員日本人なのに、ゲーム内国籍に色が出てくるのも興味深い。
人が少ないから濃い人に引っ張られやすいのか、別の何かなのか。
映画で言うと"es"なんですか、コレについてのgoodbyeさんの考察が聞いてみたいな。
ついでにgoodbyeさんの心理にも興味が
・なぜPKをやっているのか。
・ゲーム内の自らのキャラ名を晒してブログを書くのか。
・(鄭和さんへのレスを読むに)転売行為の是非はともかく、行為は悪質だと感じてらっしゃいますよね?
転載以上。話が色々盛り込まれているので、まず気になる文節ごとにレスを。
> #タガが外れているから痛い人が目立ちますが。
その‘タガ’のかなりの部分が共同幻想に基づいているんですよね。けれども、ネットゲーム内部であれば自身の‘タガが外せる’と判断してしまえる発想自体も実は丸ごと、当の共同幻想に規定されているわけです。つまり、‘ゲーム内だからという理由でタガを外した行為にでる自分’を、リアルの自分は自覚的であれ無自覚にであれ受け入れざるを得ない。けれどもそうした‘お約束’を知ってさえいれば、ゲーム内だからと‘タガ’を外してしまうのが本当は自分を貶める行為であることに気づけます。これは匿名掲示板などについても言えることです。
ポイントは、そこで貶められるものが「他者関係のなかで維持確認される自尊心」ではなく、「自分の自分自身へ向けたセルフリスペクト」であるということですね。両者の違いが分からないのは端的に幼稚さの証ですから、‘そのように見える’言動をするひとに対して周囲のプレイヤーはごく常識的に‘痛い’と感じてしまうわけです。
たとえば匿名による短絡思考の書き捨てや他者への中傷行為が、よく言われるように自身を安全圏に置いた行為ではありえず、実は自意識の基底レヴェルで深刻な自傷被害をもたらしていることに、やっている本人たちは無論気づきません。気づかないからこそどんな悪言を吐いても自分は傷つかないと誤認できるのですが、しかしそこで損なわれた、あるいは未成熟ゆえあらかじめ脆弱な自己評価こそが、その後の各人の実像をじかに形成していくという現実には抗いようがありません。
ちなみに、こうしてたかがゲームを巡って長文を巡らせるgoodbyeの身振りなどもまた、別の意味でごく常識的に‘痛い’ひとに見えているはずです。だとすれば、そんな人間のつらねる言葉を延々とここまで読み続けてきたあなた、コメントをいただいたHN“既に遅いですが。”さんではなく、コメントは書き込まずともウォッチャー感覚で面白がり今モニターに向かっているそこのあなた、もまた当然のことながら、まぎれもなく同様に、‘痛い’です。この局面では匿名性の有無が無意味化するのも、自らの行為に対しセルフリスペクトを保てているか否かこそが分水嶺になるからです。ならばもう、一緒に芝生を育ててしまうのもありですね。
> ・なぜPKをやっているのか。
そこでやや小難しい言い方のまま続けてしまいますが、ネットゲーム内部に侵入しているその共同幻想の‘輪郭’をより見極めたいというのがPK(Player Killer:他のプレイヤーを直接攻撃するひと)のスタイルをとる動機の前提にあるような気がします。このゲームを始めた初期のわたしは、「PKなんて超迷惑なだけじゃん。色付きの人らって、ちょっと頭おかしいんじゃない?」くらいに思う種のひとたちに、心情的にはむしろ近かった気がします。ただ“なぜそう思うのか”に時を待たず興味が移ったことは、いま思えばPKへの不快さを不快さのまま抱え続けるプレイヤーとの分岐点だったのかもしれません。これに続けて、↓
> ・なぜゲーム内の自らのキャラ名を晒してブログを書くのか。
キャラ名によるプレイヤーブログの存在を始めて知ったときも、「なんなんだこのひとたち、たかがゲームに入れ込み過ぎてちょっちキモイ」くらいに感じたものです。ブログというのはもっと日常や思考生活を広範に扱うものという先入観があったんですね。だからとりあえず自分でもやってみた、というのが理由の一つ。いざ始めてみると、内面的にこれはこれで継続するに足る一本の芯が通ったというのがもう一つ。
つまり当ブログの存在は3年前のわたしにとってすら、キモイ。いはんや世人にとりてをや。
> ・転売行為の是非はともかく、行為は悪質だと感じてらっしゃいますよね?
あるひとの抱えもつ‘善意’は、他者によっては通用しないケースが大いにあり得るという点で極めて主観的なものですよね。鄭和さんがコメントでそれを‘信仰’と表現された通り、その基盤には祈りにも近い深く個人的な思惟、もしくは他者に対する安易でイノセントな思い込みがあります。そしてこの基準に照らせば悪質と判断するしかないというニュアンスで、転売一般にではなく個別特定的に片桐さん(≒目の前で転売を始めてしまうスタイル)に対して、確かにわたしは悪質だと感じています。もっともそれ自体は記事中から読み取れるとしても話を俎上にのせるためのブースターに過ぎず、その行為を行為者本人が悪質と考えてやっているかどうかという別の問題こそが、個人的には関心の焦点だったわけです。
ただしこのことも、いわゆる‘中のひと’の人間性と短絡できるような直接関係はないと考えています。ここから以下、各論的なレスを一度離れます。
▼画像と予告
というわけでここからが本論部なのですが、すでに長過ぎるので一旦切って今回は終わります。続きはまたいつか。右上画像は、オスマン帝国との‘契約’前に終えたイスパニアイベントと、各国亡命行脚中の一光景です。鄭和さんとネモッティさんの画像は事前了承なしの掲載です。鄭和さんはこの記事でも再度お名前を拝借してますのでご登場いただきました。ネモさんは長く敵対私掠の間柄でしたが、実はそれ以前の低レベルの頃からフレだったりします。ないと思いますが万一画像掲載に問題あれば削除するのでお知らせを。
また今回の新記事シリーズ開始にあわせ先月の記事を事後的に「魔坑にて 壱:転売バザーの生態調査!」と改めます。記事シリーズ検索は左欄下方(テーマ別一覧)にて。
この記事シリーズは、読み手のかたからの反応によって後続するテーマを変えていきます。「壱」にいただいた反応から、見切り発車によるそうした方法もアリなのに気づきました。こうした経緯のため、「壱」へのコメントも、今後は当記事シリーズの最新記事にいただけると流れ的にまとめやすく、助かります。
忌憚ないコメントがいただければ、その流れから見えてくる新たなテーマもありそうだと期待します。ぜひ思うところをお気楽にコメントお寄せください。よろしくです。
18世紀前半、パリの最貧区に超人的な嗅覚をもった男の子が生まれ落ちます。その天性の才能はやがて、青年期のある夜に意図せず殺してしまった少女の香りによって昇華され、そこから彼の人生は‘許されざる’疾走を始めてゆきます。
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
魔坑にて 壱: 転売バザーの生態調査!
2009年2月21日 ネットゲームの魔坑にて コメント (45)
Notosサーバには「片桐ミルク」という評判の悪い転売キャラがいることは昔から知られています。以前からそのキャラの存在は気になっていたのですが、良い機会を得たので記事化してみます。
とはいえこの記事はマナー違反を超えて規約違反に当たる性格をもつため、運営によってこれを理由にgoodbyeのアカウントが強制停止される可能性も少なからずあります。しかしそうなっても試みる価値はあると判断したので掲載してみます。あくまでゲーム内公共性という範囲でのみの価値ですが、実在のキャラ名記載に至った理由も込みで、掲載意図を巡る詳細は後半に。
前回記事に続き、当然ながらややネガティヴサイドに取り込まれた物言いになります。ただし書いている動機そのものに変化はなく、明るい面があれば暗い面もあり、どっちも見たいけど暗い面を見るときは暗い言葉が並ぶ‘こともある’という以上のものではありません。
また、ネットゲームを巡るモラル問題や匿名性に起因する軋轢など比較的暗い部分に関しては、以前から当ブログで取り上げることを考えてはいました。しかしなかなか腰が上がらずにいたことも、この記事掲載に至った動機の一つになっています。ただ恒久的な掲載を意図した記事はもう少し練って書く必要を感じるため、今回の記事は数日中に削除します。本番記事では当該キャラ名を伏せる予定です。
では本題。以下の会話はジャワ海にてNPC狩り中、突然入ってきたTellから始まりました。
下記「片桐コーヒー >>>」以右は片桐さんの発言、「>> 片桐コーヒー>」以右はgoodbyeの発言です。
片桐コーヒー >>>こんにちわ。突然すみません。
>> 片桐コーヒー>?
片桐コーヒー >>>ああ、すみません。今、少しお時間よろしいですか?
>> 片桐コーヒー>なんですか
片桐コーヒー >>>この新しい仕様で、安全海域とかってなってますが。。。
片桐コーヒー >>>PKさん的に、どう捉えておられるのかな、とw
片桐コーヒー >>>ちょっとご意見をお聞きしたくて。
>> 片桐コーヒー>はい?
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。
>> 片桐コーヒー>とりあえずあなたが誰かわかりません。本キャラはどなたで?
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。これですが。。。
片桐コーヒー >>>初対面ですが。。。
片桐コーヒー >>>申し訳ございません。
片桐コーヒー >>>失礼を承知の上で。。。tellさせていただきました。
>> 片桐コーヒー>ではとりあえず言いますが、バザの値段には他の不特定プレイヤーへの善意が伴う場合があります。あなたの転売行為はそもそも失礼を超えてそうしたプレイヤーの意図を損なってます。それは本来やってる本人が苦しんでもいいことですよ。わからないかもですが。
片桐コーヒー >>>。。。ん?
片桐コーヒー >>>何か被害でも被られましたかな?
片桐コーヒー >>>もしそうであれば、申し訳ございません。
片桐コーヒー >>>具体的に言っていただければ、改善いたしますが。
>> 片桐コーヒー>べつに私個人がどうではなく、けっこう有名ですよw
片桐コーヒー >>>ええ、有名なのは知ってますw
片桐コーヒー >>>2chでも一時、叩かれてましたからw
>> 片桐コーヒー>まあわかったうえでやってるんでしょうけど、PKと同じで傷つくひとは傷ついてますよね。自覚的ならそれ以上言うこともないですけど。
片桐コーヒー >>>ええ、そうだと思いますよ。
物資を補給しました
片桐コーヒー >>>あくまでも仕様の中です。
>> 片桐コーヒー>いやそこは個人的にどうでもいい問題で、安く提供しようとしてる他人の善意を消去してることについて何か思うところがあるのか何も思わないのかが伺いたいところなんです。
片桐コーヒー >>>ああ、すみません。
片桐コーヒー >>>悪質な転売行為の報いなのか、突然、落ちましたww
>> 片桐コーヒー>責めてるわけじゃないですよ 単に疑問として聞いてくだされ
片桐コーヒー >>>ま、そういうゲーム内のモラルの話は個々人で言い合ってもしょーがないですよ。
片桐コーヒー >>>仕様を悪質に利用してるのならば、運営側に改善を求めるべきです。
>> 片桐コーヒー>いや、いまは個人でどう思ってるかを聞いてみただけです。仕様の問題はどうでもよく、片桐さん個人の思考を聞いてます
片桐コーヒー >>>ええ、責められているつもりは一切ありませんので、どうぞ、ご意見を言ってくださいな。
片桐コーヒー >>>ええ、私はマーケットというのは自由意志だと考えます。
片桐コーヒー >>>マルクスの理論に則ってやっております。
>> 片桐コーヒー>いや、それはないです
片桐コーヒー >>>いえ、否定されるとか肯定されるとかそういうお話ではないです。。。
片桐コーヒー >>>私の考えを述べているだけですが。。。
片桐コーヒー >>>議論でもするおつもりですか?
片桐コーヒー >>>私個人の思考をお聞きになられたのではないですか?
>> 片桐コーヒー>社会理論と主体の審級は違いますよね。後者について聞いてみたまでです。
片桐コーヒー >>>社会理論は個人に集約されると思いますが。。。
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。何がおっしゃりたいのか。。。私の考えをお聞きしたいのでは??
片桐コーヒー >>>自分の(マジョリティ的に悪質な)行為について。。。自分の考えを述べるつもりでしたが。。。
片桐コーヒー >>>あるいは、それに対するあなたのお考えをお聞きしてもいいですし。
>> 片桐コーヒー>違います。こんなことは初学者の前提で、それでは社会学と心理学の区別が意味をなくします。つまりあなたのいまの態度はですね、単に逃げてるだけだし、本当はそのこともわかってるヘタレの言表行為にしかなってないので
片桐コーヒー >>>それは個々人について、とても生産的なことだと思います。
片桐コーヒー >>>そうですかw
片桐コーヒー >>>私のどのような態度が何から逃げているとお考えですか?
>> 片桐コーヒー>なんだと思います?
片桐コーヒー >>>ぜひ、教えてくださいなw
片桐コーヒー >>>逃げているつもりはまったくありませんのでw
片桐コーヒー >>>でも、無意識に逃げてることも、もちろんあるでしょうな。
>> 片桐コーヒー>ご自分が、自分でわかってるのに認めない何かを指摘されても認めないひとである可能性についてはどう考えます?
片桐コーヒー >>>ええ、もう少しわかりやすく言っていただけませんか? 学がないもので。
片桐コーヒー >>>具体的事象で言ってくださいなw
>> 片桐コーヒー>学がない人間がゲームにマルクスだのマーケット理論だのを持ち込めるわけないでしょう
片桐コーヒー >>>あの。。。話を逸らさないでくださいw
片桐コーヒー >>>学があるかないか は マルクスを運用できるかできないか ではありませんでしょうw
>> 片桐コーヒー>「具体的事象で言ってくださいなw」「あの。。。話を逸らさないでくださいw」というセリフ自体があなたの態度を明確に表出している、ということは前述したとおりです
片桐コーヒー >>>うん、意味がわかりませんw
>> 片桐コーヒー>私的にはすでに聞いてみたいことは聞き出せたので、あとは関心のわく範囲で応答してるだけです。わからないならそれまでですね^^
片桐コーヒー >>>あ、聞き出せたのですか。それはよかったですw
>> 片桐コーヒー>はい
片桐コーヒー >>>じゃ、私の最初の質問にもお答えいただければ幸いですが。。。
>> 片桐コーヒー>安全海域?
片桐コーヒー >>>ええ、そうです。
片桐コーヒー >>>今回のUP(特に海域)について、PKさんがどのように思われているのか。
>> 片桐コーヒー>PK一般の立場を聞く相手としてわたしにTellしてきた時点で能登の古株さんとしてはけっこう微妙な気がしますが
片桐コーヒー >>>いえ。。。そのとき、同じ海域に あなた しかいませんでしたのでww
>> 片桐コーヒー>特になんとも思わないです。
片桐コーヒー >>>あ、そうですか。ありがとうございました。
片桐コーヒー >>>お時間を取らせてしまって、すみませんでした。では失礼します。
片桐コーヒー >>>ちなみに、お時間を取ったのはあなたの質問内容の方でしたがw
>> 片桐コーヒー>いえ、いいネタになりました
片桐コーヒー >>>またどこかでお会いしましょう。いいお話ができましたよ。
>> 片桐コーヒー>はい では~
片桐コーヒー >>>では、失礼します。よい航海を~
転売行為自体は仕様上は現に認められている行為で、チャット中にもあるようにその行為自体について否定しようとは思わないし、個人視点で否定することに意味があるとも思いません。ただし、その存在に興味はありました。仕様上は認められているけれど、プレイヤーによっては心理的な被害を大きく被り得るという点で、転売キャラの存在はPK(≒対人海賊)キャラのそれに似ています。他プレイヤーの感情領域に土足で押し入る点ではゲーム外サイトでの晒し行為にも共通する要素があります。
プレイヤーブログや匿名掲示板上でPKのキャラ名が本人の了承なしに頻繁に飛び交うのはこうした通底要素があるためですが、以上のことから同じ要素は転売キャラについても認められると考えます。試行的にとはいえ当記事で実在のキャラ名を本人の了承なしに掲載することを決めたのはこのためです。
ネットゲームは、実社会での顔を隠したゲーム内人格によりヴァーチャルな人間関係/社会を仮構できることが魅力の一つになっていますが、それは必然的にある種の人々についてその実生活ではまず表に出ないだろう暗い側面が湧出される契機にもなりえます。それは実のところ、わたしにとってネットゲームをプレイするうえで最も興味が惹かれる“具体的事象”(↑片桐さんの用語より)の一つでもあります。上記の交信について言えば、本人は軽い皮肉なり、流れのなかの何気ない応答のつもりで発したセリフに顕現しているものこそが、わたしの見たかったものの片鱗だったりします。チャット中の‘私的にはすでに聞いてみたいことは聞き出せた’とはそれを意味します。たとえば以下の2行のように。
片桐コーヒー >>>悪質な転売行為の報いなのか、突然、落ちましたww
片桐コーヒー >>>でも、無意識に逃げてることも、もちろんあるでしょうな。
ちなみに、実は片桐ミルクさんと片桐コーヒーさんの中の人が同一人物という確証はまったくなしに会話を始めています。けれどそのブラフが効いたのか否か、拍子ぬけするくらいあっさり認めていただけました。あとこのひとの主張そのものにも少し言及すると、こうした転売行為の存在はトータルでみれば単に相場を上げる効果をもたらすだけでマルクスの運用も糞もないのですが、実存の問題とシステムの問題との境界すら認識できていない時点で彼の理屈は語るに落ちる以前にそも他人と議論できる最低限の水準にありません。
後日、気力の乗ったときにでも改めて本番の記事シリーズを始められればと思います。いま思い付ける範囲で言えば、ゲーム内世界における匿名性/実名性問題や、ブログなどゲーム外部でのプレイヤー同士の争い、RMT(リアルマネートレード)、ネットゲームによる社会疎外促進の可能性等々がテーマになりそうです。いつ始める気になるかは、謎です。
とはいえこの記事はマナー違反を超えて規約違反に当たる性格をもつため、運営によってこれを理由にgoodbyeのアカウントが強制停止される可能性も少なからずあります。しかしそうなっても試みる価値はあると判断したので掲載してみます。あくまでゲーム内公共性という範囲でのみの価値ですが、実在のキャラ名記載に至った理由も込みで、掲載意図を巡る詳細は後半に。
前回記事に続き、当然ながらややネガティヴサイドに取り込まれた物言いになります。ただし書いている動機そのものに変化はなく、明るい面があれば暗い面もあり、どっちも見たいけど暗い面を見るときは暗い言葉が並ぶ‘こともある’という以上のものではありません。
また、ネットゲームを巡るモラル問題や匿名性に起因する軋轢など比較的暗い部分に関しては、以前から当ブログで取り上げることを考えてはいました。しかしなかなか腰が上がらずにいたことも、この記事掲載に至った動機の一つになっています。ただ恒久的な掲載を意図した記事はもう少し練って書く必要を感じるため、今回の記事は数日中に削除します。本番記事では当該キャラ名を伏せる予定です。
では本題。以下の会話はジャワ海にてNPC狩り中、突然入ってきたTellから始まりました。
下記「片桐コーヒー >>>」以右は片桐さんの発言、「>> 片桐コーヒー>」以右はgoodbyeの発言です。
片桐コーヒー >>>こんにちわ。突然すみません。
>> 片桐コーヒー>?
片桐コーヒー >>>ああ、すみません。今、少しお時間よろしいですか?
>> 片桐コーヒー>なんですか
片桐コーヒー >>>この新しい仕様で、安全海域とかってなってますが。。。
片桐コーヒー >>>PKさん的に、どう捉えておられるのかな、とw
片桐コーヒー >>>ちょっとご意見をお聞きしたくて。
>> 片桐コーヒー>はい?
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。
>> 片桐コーヒー>とりあえずあなたが誰かわかりません。本キャラはどなたで?
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。これですが。。。
片桐コーヒー >>>初対面ですが。。。
片桐コーヒー >>>申し訳ございません。
片桐コーヒー >>>失礼を承知の上で。。。tellさせていただきました。
>> 片桐コーヒー>ではとりあえず言いますが、バザの値段には他の不特定プレイヤーへの善意が伴う場合があります。あなたの転売行為はそもそも失礼を超えてそうしたプレイヤーの意図を損なってます。それは本来やってる本人が苦しんでもいいことですよ。わからないかもですが。
片桐コーヒー >>>。。。ん?
片桐コーヒー >>>何か被害でも被られましたかな?
片桐コーヒー >>>もしそうであれば、申し訳ございません。
片桐コーヒー >>>具体的に言っていただければ、改善いたしますが。
>> 片桐コーヒー>べつに私個人がどうではなく、けっこう有名ですよw
片桐コーヒー >>>ええ、有名なのは知ってますw
片桐コーヒー >>>2chでも一時、叩かれてましたからw
>> 片桐コーヒー>まあわかったうえでやってるんでしょうけど、PKと同じで傷つくひとは傷ついてますよね。自覚的ならそれ以上言うこともないですけど。
片桐コーヒー >>>ええ、そうだと思いますよ。
物資を補給しました
片桐コーヒー >>>あくまでも仕様の中です。
>> 片桐コーヒー>いやそこは個人的にどうでもいい問題で、安く提供しようとしてる他人の善意を消去してることについて何か思うところがあるのか何も思わないのかが伺いたいところなんです。
片桐コーヒー >>>ああ、すみません。
片桐コーヒー >>>悪質な転売行為の報いなのか、突然、落ちましたww
>> 片桐コーヒー>責めてるわけじゃないですよ 単に疑問として聞いてくだされ
片桐コーヒー >>>ま、そういうゲーム内のモラルの話は個々人で言い合ってもしょーがないですよ。
片桐コーヒー >>>仕様を悪質に利用してるのならば、運営側に改善を求めるべきです。
>> 片桐コーヒー>いや、いまは個人でどう思ってるかを聞いてみただけです。仕様の問題はどうでもよく、片桐さん個人の思考を聞いてます
片桐コーヒー >>>ええ、責められているつもりは一切ありませんので、どうぞ、ご意見を言ってくださいな。
片桐コーヒー >>>ええ、私はマーケットというのは自由意志だと考えます。
片桐コーヒー >>>マルクスの理論に則ってやっております。
>> 片桐コーヒー>いや、それはないです
片桐コーヒー >>>いえ、否定されるとか肯定されるとかそういうお話ではないです。。。
片桐コーヒー >>>私の考えを述べているだけですが。。。
片桐コーヒー >>>議論でもするおつもりですか?
片桐コーヒー >>>私個人の思考をお聞きになられたのではないですか?
>> 片桐コーヒー>社会理論と主体の審級は違いますよね。後者について聞いてみたまでです。
片桐コーヒー >>>社会理論は個人に集約されると思いますが。。。
片桐コーヒー >>>えーーっと。。。何がおっしゃりたいのか。。。私の考えをお聞きしたいのでは??
片桐コーヒー >>>自分の(マジョリティ的に悪質な)行為について。。。自分の考えを述べるつもりでしたが。。。
片桐コーヒー >>>あるいは、それに対するあなたのお考えをお聞きしてもいいですし。
>> 片桐コーヒー>違います。こんなことは初学者の前提で、それでは社会学と心理学の区別が意味をなくします。つまりあなたのいまの態度はですね、単に逃げてるだけだし、本当はそのこともわかってるヘタレの言表行為にしかなってないので
片桐コーヒー >>>それは個々人について、とても生産的なことだと思います。
片桐コーヒー >>>そうですかw
片桐コーヒー >>>私のどのような態度が何から逃げているとお考えですか?
>> 片桐コーヒー>なんだと思います?
片桐コーヒー >>>ぜひ、教えてくださいなw
片桐コーヒー >>>逃げているつもりはまったくありませんのでw
片桐コーヒー >>>でも、無意識に逃げてることも、もちろんあるでしょうな。
>> 片桐コーヒー>ご自分が、自分でわかってるのに認めない何かを指摘されても認めないひとである可能性についてはどう考えます?
片桐コーヒー >>>ええ、もう少しわかりやすく言っていただけませんか? 学がないもので。
片桐コーヒー >>>具体的事象で言ってくださいなw
>> 片桐コーヒー>学がない人間がゲームにマルクスだのマーケット理論だのを持ち込めるわけないでしょう
片桐コーヒー >>>あの。。。話を逸らさないでくださいw
片桐コーヒー >>>学があるかないか は マルクスを運用できるかできないか ではありませんでしょうw
>> 片桐コーヒー>「具体的事象で言ってくださいなw」「あの。。。話を逸らさないでくださいw」というセリフ自体があなたの態度を明確に表出している、ということは前述したとおりです
片桐コーヒー >>>うん、意味がわかりませんw
>> 片桐コーヒー>私的にはすでに聞いてみたいことは聞き出せたので、あとは関心のわく範囲で応答してるだけです。わからないならそれまでですね^^
片桐コーヒー >>>あ、聞き出せたのですか。それはよかったですw
>> 片桐コーヒー>はい
片桐コーヒー >>>じゃ、私の最初の質問にもお答えいただければ幸いですが。。。
>> 片桐コーヒー>安全海域?
片桐コーヒー >>>ええ、そうです。
片桐コーヒー >>>今回のUP(特に海域)について、PKさんがどのように思われているのか。
>> 片桐コーヒー>PK一般の立場を聞く相手としてわたしにTellしてきた時点で能登の古株さんとしてはけっこう微妙な気がしますが
片桐コーヒー >>>いえ。。。そのとき、同じ海域に あなた しかいませんでしたのでww
>> 片桐コーヒー>特になんとも思わないです。
片桐コーヒー >>>あ、そうですか。ありがとうございました。
片桐コーヒー >>>お時間を取らせてしまって、すみませんでした。では失礼します。
片桐コーヒー >>>ちなみに、お時間を取ったのはあなたの質問内容の方でしたがw
>> 片桐コーヒー>いえ、いいネタになりました
片桐コーヒー >>>またどこかでお会いしましょう。いいお話ができましたよ。
>> 片桐コーヒー>はい では~
片桐コーヒー >>>では、失礼します。よい航海を~
転売行為自体は仕様上は現に認められている行為で、チャット中にもあるようにその行為自体について否定しようとは思わないし、個人視点で否定することに意味があるとも思いません。ただし、その存在に興味はありました。仕様上は認められているけれど、プレイヤーによっては心理的な被害を大きく被り得るという点で、転売キャラの存在はPK(≒対人海賊)キャラのそれに似ています。他プレイヤーの感情領域に土足で押し入る点ではゲーム外サイトでの晒し行為にも共通する要素があります。
プレイヤーブログや匿名掲示板上でPKのキャラ名が本人の了承なしに頻繁に飛び交うのはこうした通底要素があるためですが、以上のことから同じ要素は転売キャラについても認められると考えます。試行的にとはいえ当記事で実在のキャラ名を本人の了承なしに掲載することを決めたのはこのためです。
ネットゲームは、実社会での顔を隠したゲーム内人格によりヴァーチャルな人間関係/社会を仮構できることが魅力の一つになっていますが、それは必然的にある種の人々についてその実生活ではまず表に出ないだろう暗い側面が湧出される契機にもなりえます。それは実のところ、わたしにとってネットゲームをプレイするうえで最も興味が惹かれる“具体的事象”(↑片桐さんの用語より)の一つでもあります。上記の交信について言えば、本人は軽い皮肉なり、流れのなかの何気ない応答のつもりで発したセリフに顕現しているものこそが、わたしの見たかったものの片鱗だったりします。チャット中の‘私的にはすでに聞いてみたいことは聞き出せた’とはそれを意味します。たとえば以下の2行のように。
片桐コーヒー >>>悪質な転売行為の報いなのか、突然、落ちましたww
片桐コーヒー >>>でも、無意識に逃げてることも、もちろんあるでしょうな。
ちなみに、実は片桐ミルクさんと片桐コーヒーさんの中の人が同一人物という確証はまったくなしに会話を始めています。けれどそのブラフが効いたのか否か、拍子ぬけするくらいあっさり認めていただけました。あとこのひとの主張そのものにも少し言及すると、こうした転売行為の存在はトータルでみれば単に相場を上げる効果をもたらすだけでマルクスの運用も糞もないのですが、実存の問題とシステムの問題との境界すら認識できていない時点で彼の理屈は語るに落ちる以前にそも他人と議論できる最低限の水準にありません。
後日、気力の乗ったときにでも改めて本番の記事シリーズを始められればと思います。いま思い付ける範囲で言えば、ゲーム内世界における匿名性/実名性問題や、ブログなどゲーム外部でのプレイヤー同士の争い、RMT(リアルマネートレード)、ネットゲームによる社会疎外促進の可能性等々がテーマになりそうです。いつ始める気になるかは、謎です。
goodbyeの船には来月後半、オスマンの緑月旗が翻っている予定です。では近況から。
▼賞金首の剣士、逃げる
最近は剣士へ転職して、NPC狩りをメインに遊んでいます。R10に満たない防御・戦術・銃撃を中心に鍛えているのですが、もちろん今さら白兵スキルに不足を感じたわけもなく、主たる目的は他にあります。溜まった録画DVDの処理と、対オスマン帝国の友好度上げですね。飽きたらお金稼ぎも兼ねて、レアハントにジャワ海方面へ出張したり。
NPC狩り自体は単調で‘ながら作業’に最適なのですが、かなりの高額で売れる重装船尾楼を3つ持った状態でPKK(海賊討伐艦隊)のかたに追いかけられるなど、賞金首ゆえのスリリングな事態もほどよく起きています。
▼スルタン謁見に向けて
PC国家としてのオスマン帝国実装が目玉の大型アップデート、とうとう来月半ばに迫りました。新PC国家の実装という意味では、実に3年半ぶりということに。
公式HPでの告知: http://www.gamecity.ne.jp/dol/cruzdelsur/ottoman.htm
旧来の6国家間におけるプレイヤー所属国の移動は“亡命”システムにより可能でしたが、オスマン帝国への移籍については表現が“契約”という言葉に変更されました。とはいえ契約に時限性があるわけでもなく、枠組みは基本的に同じ様子。呼称による外見上の差別化、歴史宗教感情への配慮、といったところでしょうか。いずれにしても、微妙、とだけ感想を述べておきます。これに限らず全体的に、こういうところで演出できる“粋”もあるのに敢えて野暮をとる方向性は、現在の開発陣に一貫してますね。
わたしがオスマン旗への移籍を決めているのは、新仕様への興味からではなく、むしろ‘大航海Online’を継続的に遊びたくなるような動機が現状ではあまり感じられずにいるからです。ならばこの規模のアップデートが必然的に惹起するだろう諸々のアンバランス設定や、それに付随して起こるだろう局所的な不条理劇の幾らかを満喫するのに最適なポジションを採ろう、という目論見ですね。
現在告知されている移籍条件は、支払うべきコストの予想外の大きさが、移籍に前々から関心のあったプレイヤーの多くを逡巡させているようです。けれども個人的には、そうした迷いが持てることを逆に羨ましくも思います。昨年は都合4回しか課金しませんでした。コストの大きさゆえ移籍を諦めたとして、現状が続くだけなら今年はさらに課金回数も減ることでしょう。思い入れのあるゲームだけに、これはとても残念な事態なのです。ゆえに、オスマン。
アミバ様の木人形狩り日誌: http://amibasama.seesaa.net/article/112699276.html
すでに告知のある新要素についての個別の感想は割愛。代わりに古参プレイヤーが抱く意見の一例を紹介しておきます(↑前後にも関連記事があり)。総じて毒舌調ですが、公式HPでの告知を古参プレイヤーの立場から論理的に捉えれば大体そうなるという思考が、よく網羅されていると思います。ちなみにアミバ様は、Notosサーバの古株なら恐らく誰もが知る名物プレイヤーです。(仮面的に)
▼開発者インタヴューの怪
個人的に気になるのは個別の設定がどうこうという話より、全体として最近のアップデートの目指す方向性がさっぱり見えないことです。見えない以上、共感することも楽しみに待つこともありえません。たとえば大型アップデートの前には4Gamer.netによる開発担当者2名へのインタヴュー掲載(↓)が恒例になっていますが、少なくない古参プレイヤーの目にはこれが胡散臭く映って失笑を買うのもまた‘恒例’になっています。
4Gamer.net: http://www.4gamer.net/games/013/G001372/20081225077/
教祖blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1385.html
最近のインタヴューにもその徴候は顕著に表れています。たとえば直近のアップデートに関して毎回登場する「プレイヤーの皆さんに大変喜ばれた」「ご満足いただけた」といった類の発言。これは既存のプレイヤー向けというよりは、この記事を機にプレイを始めるかもしれない4Gamer.net読者へ向けられたものと考えられます。十把一絡にされた既存のプレイヤーとしては、そう受け取らなければ不快に感じるひとすら少なからずいるはずです。しかし潜在的な新規プレイヤーへのPRとして、今回の4ページにも渡る長文はどうみても不適切です。
ではやはり既存プレイヤー向け‘でも’あったのか。無論そうなのでしょうが、しかしプレイ履歴の長い人間であれば、この二人の発言には外向きの誇張が大量に含まれていることは遠い昔に誰しも気づいているはずです。実際にその言葉にどれだけの内実があるかが問題なのではなく、そのように感じさせてしまう発言を常とすることが、読み取れる意図に照らせば相当に不可解なのですね。
いま新しいネットゲームを始めようと思ったら、まず公式HPを検索するなどしてそれがどんなゲームかを確認しますよね。同様にどれくらい面白そうなのかは、実際にプレイしているひとのブログなりSNSでの感想なりを探したうえで推し量るものだと思います。ソフト産業における広告戦略においてユーザーの声ほど決定的なものが他にないことは、各種娯楽産業の行う口コミ戦術やAmazon等の品評システムを持ち出すまでもなく明らかでしょう。
しかしそのユーザーサイドの肉声による文章に、例えば上掲の教祖ブログ(←各種検索サイトにおいてこのジャンルの最上位にランクされやすいブログの一つ)における皮肉のように、あるいは以前話題になった、この二人をモデルとするAA(アスキーアート)に代表される嘲笑的な反応が並んでいればどうでしょうか。そうなれば新規巻き込みの目的としても、既存プレイヤーへのアピールとしても、インタヴューでの二人の見せ方は上策ではなかったということになります。
話を元に戻すと、長いスパンでの拡張計画に対して既存プレイヤーがまず何よりも望むのは、やや抽象的に言えばできるだけ齟齬の少ない流れのなかに自分のキャラを位置づけられる“見取り図”のようなものではないかと思います。要はグランドデザインの提示なのですが、外観的には‘ゲーム世界がこうなる頃には、自分のキャラはこういう方向へ持っていこう’というようにプレイヤー各自が抱く物語のメディウムになりうる形でアウトプットされる必要があるはずです。直近のインタヴューで最もそれに近い発言は、1ページ目の中段にあるので以下に一部を引用します。
“「Cruz del Sur」最初のアップデートが世界一周をするというコンセプトから始まったのであれば,その締めとなる部分は……やっぱり世界一周の旅を終えたいですよね。”
……‘その締め’がオスマン帝国実装であるという物語は、果たして既存プレイヤーに対するインセンティヴとしてどれほど機能するのでしょうか。あるいは発言の意図は別にあったのでしょうか。何を言うべきかおぼろげに分かっていながら、そのための言葉を準備しきれていない、そういう印象すら受けてしまいます。わたしにとってそれは、メガネの男性が毎度繰り返すこじつけめいたセリフともども、やはり謎のままなのです。
▼おまけ
ちょっと今回、マイナスオーラが出すぎたかも。でも、開発資金力より発想の問題、みたいなところが目につくと、もったいないよな~、残念だな~、って思っちゃうんですよね。ついでに1年前と2年前に書いたオスマン帝国実装関連の記事URLを下記に。想い続けて幾星霜。
王朝のゆくえ: http://75061.diarynote.jp/?day=20071216
麾下の破軍: http://75061.diarynote.jp/?day=20070209
「麾下の破軍」中の対人上納品を巡る新仕様については、オスマン帝国所属のプレイヤーについてのみ使用を禁じることでプレイヤーのゾーン分類ができるのではという思いつきでした。現在告知されている仕様下ではまずありえない設定ですが、直近のインタヴュー中にあるようなユーザーサイドからの要請に対しては、全プレイヤーに対し一律に発揮される費用対効果のバランスを変更するより、ゾーン分けという発想のほうがまだ効くと思います。日本実装に関しても過去記事中で言及した状況がオスマン実装によって変わるため、新たに思うところはあるのですがまたの機会に。
▼賞金首の剣士、逃げる
最近は剣士へ転職して、NPC狩りをメインに遊んでいます。R10に満たない防御・戦術・銃撃を中心に鍛えているのですが、もちろん今さら白兵スキルに不足を感じたわけもなく、主たる目的は他にあります。溜まった録画DVDの処理と、対オスマン帝国の友好度上げですね。飽きたらお金稼ぎも兼ねて、レアハントにジャワ海方面へ出張したり。
NPC狩り自体は単調で‘ながら作業’に最適なのですが、かなりの高額で売れる重装船尾楼を3つ持った状態でPKK(海賊討伐艦隊)のかたに追いかけられるなど、賞金首ゆえのスリリングな事態もほどよく起きています。
▼スルタン謁見に向けて
PC国家としてのオスマン帝国実装が目玉の大型アップデート、とうとう来月半ばに迫りました。新PC国家の実装という意味では、実に3年半ぶりということに。
公式HPでの告知: http://www.gamecity.ne.jp/dol/cruzdelsur/ottoman.htm
旧来の6国家間におけるプレイヤー所属国の移動は“亡命”システムにより可能でしたが、オスマン帝国への移籍については表現が“契約”という言葉に変更されました。とはいえ契約に時限性があるわけでもなく、枠組みは基本的に同じ様子。呼称による外見上の差別化、歴史宗教感情への配慮、といったところでしょうか。いずれにしても、微妙、とだけ感想を述べておきます。これに限らず全体的に、こういうところで演出できる“粋”もあるのに敢えて野暮をとる方向性は、現在の開発陣に一貫してますね。
わたしがオスマン旗への移籍を決めているのは、新仕様への興味からではなく、むしろ‘大航海Online’を継続的に遊びたくなるような動機が現状ではあまり感じられずにいるからです。ならばこの規模のアップデートが必然的に惹起するだろう諸々のアンバランス設定や、それに付随して起こるだろう局所的な不条理劇の幾らかを満喫するのに最適なポジションを採ろう、という目論見ですね。
現在告知されている移籍条件は、支払うべきコストの予想外の大きさが、移籍に前々から関心のあったプレイヤーの多くを逡巡させているようです。けれども個人的には、そうした迷いが持てることを逆に羨ましくも思います。昨年は都合4回しか課金しませんでした。コストの大きさゆえ移籍を諦めたとして、現状が続くだけなら今年はさらに課金回数も減ることでしょう。思い入れのあるゲームだけに、これはとても残念な事態なのです。ゆえに、オスマン。
アミバ様の木人形狩り日誌: http://amibasama.seesaa.net/article/112699276.html
すでに告知のある新要素についての個別の感想は割愛。代わりに古参プレイヤーが抱く意見の一例を紹介しておきます(↑前後にも関連記事があり)。総じて毒舌調ですが、公式HPでの告知を古参プレイヤーの立場から論理的に捉えれば大体そうなるという思考が、よく網羅されていると思います。ちなみにアミバ様は、Notosサーバの古株なら恐らく誰もが知る名物プレイヤーです。(仮面的に)
▼開発者インタヴューの怪
個人的に気になるのは個別の設定がどうこうという話より、全体として最近のアップデートの目指す方向性がさっぱり見えないことです。見えない以上、共感することも楽しみに待つこともありえません。たとえば大型アップデートの前には4Gamer.netによる開発担当者2名へのインタヴュー掲載(↓)が恒例になっていますが、少なくない古参プレイヤーの目にはこれが胡散臭く映って失笑を買うのもまた‘恒例’になっています。
4Gamer.net: http://www.4gamer.net/games/013/G001372/20081225077/
教祖blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1385.html
最近のインタヴューにもその徴候は顕著に表れています。たとえば直近のアップデートに関して毎回登場する「プレイヤーの皆さんに大変喜ばれた」「ご満足いただけた」といった類の発言。これは既存のプレイヤー向けというよりは、この記事を機にプレイを始めるかもしれない4Gamer.net読者へ向けられたものと考えられます。十把一絡にされた既存のプレイヤーとしては、そう受け取らなければ不快に感じるひとすら少なからずいるはずです。しかし潜在的な新規プレイヤーへのPRとして、今回の4ページにも渡る長文はどうみても不適切です。
ではやはり既存プレイヤー向け‘でも’あったのか。無論そうなのでしょうが、しかしプレイ履歴の長い人間であれば、この二人の発言には外向きの誇張が大量に含まれていることは遠い昔に誰しも気づいているはずです。実際にその言葉にどれだけの内実があるかが問題なのではなく、そのように感じさせてしまう発言を常とすることが、読み取れる意図に照らせば相当に不可解なのですね。
いま新しいネットゲームを始めようと思ったら、まず公式HPを検索するなどしてそれがどんなゲームかを確認しますよね。同様にどれくらい面白そうなのかは、実際にプレイしているひとのブログなりSNSでの感想なりを探したうえで推し量るものだと思います。ソフト産業における広告戦略においてユーザーの声ほど決定的なものが他にないことは、各種娯楽産業の行う口コミ戦術やAmazon等の品評システムを持ち出すまでもなく明らかでしょう。
しかしそのユーザーサイドの肉声による文章に、例えば上掲の教祖ブログ(←各種検索サイトにおいてこのジャンルの最上位にランクされやすいブログの一つ)における皮肉のように、あるいは以前話題になった、この二人をモデルとするAA(アスキーアート)に代表される嘲笑的な反応が並んでいればどうでしょうか。そうなれば新規巻き込みの目的としても、既存プレイヤーへのアピールとしても、インタヴューでの二人の見せ方は上策ではなかったということになります。
話を元に戻すと、長いスパンでの拡張計画に対して既存プレイヤーがまず何よりも望むのは、やや抽象的に言えばできるだけ齟齬の少ない流れのなかに自分のキャラを位置づけられる“見取り図”のようなものではないかと思います。要はグランドデザインの提示なのですが、外観的には‘ゲーム世界がこうなる頃には、自分のキャラはこういう方向へ持っていこう’というようにプレイヤー各自が抱く物語のメディウムになりうる形でアウトプットされる必要があるはずです。直近のインタヴューで最もそれに近い発言は、1ページ目の中段にあるので以下に一部を引用します。
“「Cruz del Sur」最初のアップデートが世界一周をするというコンセプトから始まったのであれば,その締めとなる部分は……やっぱり世界一周の旅を終えたいですよね。”
……‘その締め’がオスマン帝国実装であるという物語は、果たして既存プレイヤーに対するインセンティヴとしてどれほど機能するのでしょうか。あるいは発言の意図は別にあったのでしょうか。何を言うべきかおぼろげに分かっていながら、そのための言葉を準備しきれていない、そういう印象すら受けてしまいます。わたしにとってそれは、メガネの男性が毎度繰り返すこじつけめいたセリフともども、やはり謎のままなのです。
▼おまけ
ちょっと今回、マイナスオーラが出すぎたかも。でも、開発資金力より発想の問題、みたいなところが目につくと、もったいないよな~、残念だな~、って思っちゃうんですよね。ついでに1年前と2年前に書いたオスマン帝国実装関連の記事URLを下記に。想い続けて幾星霜。
王朝のゆくえ: http://75061.diarynote.jp/?day=20071216
麾下の破軍: http://75061.diarynote.jp/?day=20070209
「麾下の破軍」中の対人上納品を巡る新仕様については、オスマン帝国所属のプレイヤーについてのみ使用を禁じることでプレイヤーのゾーン分類ができるのではという思いつきでした。現在告知されている仕様下ではまずありえない設定ですが、直近のインタヴュー中にあるようなユーザーサイドからの要請に対しては、全プレイヤーに対し一律に発揮される費用対効果のバランスを変更するより、ゾーン分けという発想のほうがまだ効くと思います。日本実装に関しても過去記事中で言及した状況がオスマン実装によって変わるため、新たに思うところはあるのですがまたの機会に。
Job Description 16: 熟練剣士 【アラトリステ】
2009年1月21日 就職・転職 コメント (6)
17世紀前半、スペインは隣国ポルトガルを併合し、アルマダの海戦に敗れつつもいまだ世界の覇権を掌中に収めていました。しかしフランドルでのオランダとの戦争はいつまでも絶えることがなく(八十年戦争)、やがて西仏戦争が勃発、カタルーニャやポルトガルでは大規模な反乱も起きるなど、その繁栄には少しずつ翳りが差し始めます。スペイン映画“アラトリステ”では、こうした時代のイベリア半島を駆け抜けた一人の剣士の生涯が描かれました。
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
“成績不振で大会の出場が危うく、参加する為に自らの肉体を差し出す。” 今回のキーフレーズです。
さて若干の休止を挟み、今年3回目のプレイ期間継続中。いまは散発的に妙な時と場所に出没する小物海賊をやってます。去年まで活動のメインだった週末の定例模擬は、諸事情が重なり出にくくなったこともあり休止。今回の記事は以下近況まとめなど。
▼猫で大海戦
個人的に9ヵ月ぶりの大海戦、今回は所属する猫教団の商会艦隊で出てみました。楽しい感じの表現は商会長のブログのほうが巧いので、気が向いたら下記URLをご参照あれ↓
教祖Blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1333.html
全参加はきついので中日だけのつもりでしたが、意外にやる気が出て最終日も登板。千秋楽は中大旗艦で与撃沈数もトップと好き勝手にやらせてもらいました。
毎回MVPを競うのが当たり前の脳筋艦隊に長くいたためフラストレーションが貯まるかなとも思ったのですが、ふだん模擬はしてなくても大海戦の参戦歴は長いメンバーが中核を固めていたので、驚くほど快適に旗艦業務へ専念できた感じです。もじゃさんによる下掲動画は中日の大型戦。9分40秒あたりから相手の旗艦と延々白兵が続いてじんわり涙目なgoodbyeが映ってます。全体的にいろいろ新鮮で楽しめました。
もじゃさんによる動画: http://zoome.jp/mojas/diary/103/
▼猫が対抗戦
先週にはセビリアのライヴァル商会“いらん子”との対抗戦も。開始の夜10時にはすでに1時間ほど寝てたのも禍いして、実は猛烈に眠くて戦闘の内容もよく覚えてなかったり。眠気防止のため無駄にたくさんチャットしてたのは覚えてます。ちなみに上記に挙げたもじゃさんはいらん子所属なので、同ページから対抗戦の動画も観られます。下記Fairy商会は別サーバの商会ですが、筆者の‘り(仮名)’さんはサーバを越えひそかに猫教団にも所属してたりします。
猫教団Blog: http://neko6.blog18.fc2.com/blog-entry-288.html
教祖Blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1349.html
Fairy商会ブログ: http://fairycompany.blog64.fc2.com/blog-entry-1089.html
続いて罰ゲームの商会宣伝。いらん子いいですよいらん子。何もいらないんですから。
▼小海賊あらわる
2年ぶりに対人海賊をやっています。暗黒面にすべり堕ちました。上納品の実装以降はたぶん初めて。方針は概ね2年前に重なります。詳細は過去記事にて↓
「常在戦章」: http://goodbye.diarynote.jp/200607191718530000/
ただし今回はかなりアバウトで、言語も気分しだいで日本語も使えば似非中国語も使ってます。ソロのイスパニア私掠という根幹は変わりませんが、時によりフランス船や複合艦隊にイスパニア船がいる場合でも襲撃対象に入れることも。詳述はしませんが以前に比べ全体の人口密度が格段に下がり、複数アカウント+複数国船籍による個人艦隊が明らかに増えたことがその主な理由で、1ヶ月ほどやってみて次第にそうなりました。
2年前は収奪行為や国籍RP(敵対国を意識するRole Playing)そのものが目的でしたが、今回の関心はこのゲームの現状についての極私的思念から実際のエンカウントへと至るプロセス全体にある感じで、この影響もあって海域を隔てるような長距離移動を経ての交戦が多くなりました。ただこれをやると隣接海域の風向きを読み遠洋まで追い詰めた上でいわゆる“ログアウト逃げ”をよくされるのがご愛敬といったところでしょうか。わたしはそれ自体を達成と感じられるのでさほど不満はないのですが、収奪目的の海賊プレイヤーにはつらいだろうと思います。このあたりも遠洋での高速化の修正以降、集団化して狩りだすひとが相対的にさらに増え、ソロPK(Player Killing/Killer)が減っている原因の一つかもしれません。
こうしたプレイ動機の変化のため、以前と異なり討伐艦隊(PKK艦隊)の相手は基本的にしなくなりましたが、これも気分次第。ソロで戦う旨宣言されたら興が乗ってしまい軽艤装でも受けて立つ可能性は高いです。いまのところPKKグループに一度、ソロ軍人さんの機雷に一度沈められてしまいました。これだけで計700万Dの賞金献上。小物海賊も楽ではありません。
また収奪品を不要と判断した場合や、相手にとって思い入れが感じられるものだった場合その場でトレードボタンを押しています。なんだかんだで2回に1回は返してるかも。これはPKKの船を警戒する必要から説明なしにやってます。あのトレード申請は謎だったという被害者のかたがこのブログを検索してくる可能性もあるでしょうから一応書いておきます。
▼おまけのアクセス解析
このDiary Noteには中途半端なアクセス解析機能がついていて、各種検索サイトでどのような語句を引いてこのブログに飛んできたかわかるようになってます。記事内容を反映してこのブログへは歴史・航海用語関連で訪れるかたが多いのですが、たまに物凄い検索履歴があったりします。そんななかでも最近あった超弩級のものが、冒頭のフレーズなのでした↓
「成績不振で大会の出場が危うく、参加する為に自らの肉体を差し出す。」
この文章でグーグルを検索してみてください。当ブログがなぜか堂々の2位にランクイン! ニフティー検索でも2位(涙)。過去にも「金髪軍人娘」や「小学生の肉奴隷」などを求めてこのブログにたどり着いたかたがいましたが、今回はそれらよりも数段上の衝撃が走りました。さっぱり意味がわかりません。差し出したこともたぶんありません。
それから今日あったのが、「直線実長視副投影図」。これはこれでちょっぴりエッチかも。いやいやいや。
さて若干の休止を挟み、今年3回目のプレイ期間継続中。いまは散発的に妙な時と場所に出没する小物海賊をやってます。去年まで活動のメインだった週末の定例模擬は、諸事情が重なり出にくくなったこともあり休止。今回の記事は以下近況まとめなど。
▼猫で大海戦
個人的に9ヵ月ぶりの大海戦、今回は所属する猫教団の商会艦隊で出てみました。楽しい感じの表現は商会長のブログのほうが巧いので、気が向いたら下記URLをご参照あれ↓
教祖Blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1333.html
全参加はきついので中日だけのつもりでしたが、意外にやる気が出て最終日も登板。千秋楽は中大旗艦で与撃沈数もトップと好き勝手にやらせてもらいました。
毎回MVPを競うのが当たり前の脳筋艦隊に長くいたためフラストレーションが貯まるかなとも思ったのですが、ふだん模擬はしてなくても大海戦の参戦歴は長いメンバーが中核を固めていたので、驚くほど快適に旗艦業務へ専念できた感じです。もじゃさんによる下掲動画は中日の大型戦。9分40秒あたりから相手の旗艦と延々白兵が続いてじんわり涙目なgoodbyeが映ってます。全体的にいろいろ新鮮で楽しめました。
もじゃさんによる動画: http://zoome.jp/mojas/diary/103/
▼猫が対抗戦
先週にはセビリアのライヴァル商会“いらん子”との対抗戦も。開始の夜10時にはすでに1時間ほど寝てたのも禍いして、実は猛烈に眠くて戦闘の内容もよく覚えてなかったり。眠気防止のため無駄にたくさんチャットしてたのは覚えてます。ちなみに上記に挙げたもじゃさんはいらん子所属なので、同ページから対抗戦の動画も観られます。下記Fairy商会は別サーバの商会ですが、筆者の‘り(仮名)’さんはサーバを越えひそかに猫教団にも所属してたりします。
猫教団Blog: http://neko6.blog18.fc2.com/blog-entry-288.html
教祖Blog in Notos: http://nekokyoudan.blog14.fc2.com/blog-entry-1349.html
Fairy商会ブログ: http://fairycompany.blog64.fc2.com/blog-entry-1089.html
続いて罰ゲームの商会宣伝。いらん子いいですよいらん子。何もいらないんですから。
▼小海賊あらわる
2年ぶりに対人海賊をやっています。暗黒面にすべり堕ちました。上納品の実装以降はたぶん初めて。方針は概ね2年前に重なります。詳細は過去記事にて↓
「常在戦章」: http://goodbye.diarynote.jp/200607191718530000/
ただし今回はかなりアバウトで、言語も気分しだいで日本語も使えば似非中国語も使ってます。ソロのイスパニア私掠という根幹は変わりませんが、時によりフランス船や複合艦隊にイスパニア船がいる場合でも襲撃対象に入れることも。詳述はしませんが以前に比べ全体の人口密度が格段に下がり、複数アカウント+複数国船籍による個人艦隊が明らかに増えたことがその主な理由で、1ヶ月ほどやってみて次第にそうなりました。
2年前は収奪行為や国籍RP(敵対国を意識するRole Playing)そのものが目的でしたが、今回の関心はこのゲームの現状についての極私的思念から実際のエンカウントへと至るプロセス全体にある感じで、この影響もあって海域を隔てるような長距離移動を経ての交戦が多くなりました。ただこれをやると隣接海域の風向きを読み遠洋まで追い詰めた上でいわゆる“ログアウト逃げ”をよくされるのがご愛敬といったところでしょうか。わたしはそれ自体を達成と感じられるのでさほど不満はないのですが、収奪目的の海賊プレイヤーにはつらいだろうと思います。このあたりも遠洋での高速化の修正以降、集団化して狩りだすひとが相対的にさらに増え、ソロPK(Player Killing/Killer)が減っている原因の一つかもしれません。
こうしたプレイ動機の変化のため、以前と異なり討伐艦隊(PKK艦隊)の相手は基本的にしなくなりましたが、これも気分次第。ソロで戦う旨宣言されたら興が乗ってしまい軽艤装でも受けて立つ可能性は高いです。いまのところPKKグループに一度、ソロ軍人さんの機雷に一度沈められてしまいました。これだけで計700万Dの賞金献上。小物海賊も楽ではありません。
また収奪品を不要と判断した場合や、相手にとって思い入れが感じられるものだった場合その場でトレードボタンを押しています。なんだかんだで2回に1回は返してるかも。これはPKKの船を警戒する必要から説明なしにやってます。あのトレード申請は謎だったという被害者のかたがこのブログを検索してくる可能性もあるでしょうから一応書いておきます。
▼おまけのアクセス解析
このDiary Noteには中途半端なアクセス解析機能がついていて、各種検索サイトでどのような語句を引いてこのブログに飛んできたかわかるようになってます。記事内容を反映してこのブログへは歴史・航海用語関連で訪れるかたが多いのですが、たまに物凄い検索履歴があったりします。そんななかでも最近あった超弩級のものが、冒頭のフレーズなのでした↓
「成績不振で大会の出場が危うく、参加する為に自らの肉体を差し出す。」
この文章でグーグルを検索してみてください。当ブログがなぜか堂々の2位にランクイン! ニフティー検索でも2位(涙)。過去にも「金髪軍人娘」や「小学生の肉奴隷」などを求めてこのブログにたどり着いたかたがいましたが、今回はそれらよりも数段上の衝撃が走りました。さっぱり意味がわかりません。差し出したこともたぶんありません。
それから今日あったのが、「直線実長視副投影図」。これはこれでちょっぴりエッチかも。いやいやいや。
当ブログサーバの大規模アップデートが先月行われました。それにあわせいくつか手を加えたのでご報告。
このDiarynoteサーバの唯一の美点は、シーラカンスのごとく不動の旧システムを維持していることだと個人的に考えていたので、今回のアップデートは非常に余計でかつ意味不明なものに映りました。
▼リンク・目次カテゴリーの分離増設
元々あったものを2つに分けました。計4記事。いずれも随時更新予定。
当ブログ内の記事インデックス: http://goodbye.diarynote.jp/?theme_id=9
一般外部サイトへのリンク集: http://goodbye.diarynote.jp/?theme_id=7
▼「お気に入り日記」の整理
さいきん更新がないもの、‘大航海時代Online’と縁がないもの、相互リンクのないもの、のうちから一部を削除しました。依然多すぎる気もしますが。
なぜ自分のブログが外されたんだ、どうしてうちのはリンクを返されないんだ、といったかたがいらしたらお知らせを。おそらく単なる見落としです。
▼その他
ヘッダー画像やトップ画像の追加変更、一部記事のカテゴリー移動、目についた誤字訂正なども行いました。2年前に書いたプロフィール欄は手をつけないことに。
goodbyeのプロフィール: http://goodbye.diarynote.jp/profile/
しかし今回のアップデート、やるにしても中途半端すぎて相当に不可解です。右カラムのレイアウトやトラックバックなどこれまであった機能が何の説明もなしに消えていたり、リンクタグ周りの仕様が一層支離滅裂になっていたり。(URLを表記しないとリンクタグを受け付けない従来の謎仕様に加え、小文字装飾などの際には一文字開けないと変換されなくなった等々) そして最も致命的に思える、事前の告知がない不定期のメンテナンスやサーバダウンが多い点には特に改善の兆しもなさそうです。
できれば2度としないでほしい。望むのはそれだけです。やるならやるで、もっと普通に。
このDiarynoteサーバの唯一の美点は、シーラカンスのごとく不動の旧システムを維持していることだと個人的に考えていたので、今回のアップデートは非常に余計でかつ意味不明なものに映りました。
▼リンク・目次カテゴリーの分離増設
元々あったものを2つに分けました。計4記事。いずれも随時更新予定。
当ブログ内の記事インデックス: http://goodbye.diarynote.jp/?theme_id=9
一般外部サイトへのリンク集: http://goodbye.diarynote.jp/?theme_id=7
▼「お気に入り日記」の整理
さいきん更新がないもの、‘大航海時代Online’と縁がないもの、相互リンクのないもの、のうちから一部を削除しました。依然多すぎる気もしますが。
なぜ自分のブログが外されたんだ、どうしてうちのはリンクを返されないんだ、といったかたがいらしたらお知らせを。おそらく単なる見落としです。
▼その他
ヘッダー画像やトップ画像の追加変更、一部記事のカテゴリー移動、目についた誤字訂正なども行いました。2年前に書いたプロフィール欄は手をつけないことに。
goodbyeのプロフィール: http://goodbye.diarynote.jp/profile/
しかし今回のアップデート、やるにしても中途半端すぎて相当に不可解です。右カラムのレイアウトやトラックバックなどこれまであった機能が何の説明もなしに消えていたり、リンクタグ周りの仕様が一層支離滅裂になっていたり。(URLを表記しないとリンクタグを受け付けない従来の謎仕様に加え、小文字装飾などの際には一文字開けないと変換されなくなった等々) そして最も致命的に思える、事前の告知がない不定期のメンテナンスやサーバダウンが多い点には特に改善の兆しもなさそうです。
できれば2度としないでほしい。望むのはそれだけです。やるならやるで、もっと普通に。
史上名高い“アルマダの海戦”の勃発前夜から終結に到るまでをエリザベス1世の視点から描いた2007年公開の本作は、1998年製作の映画“エリザベス”の続編として構想されました。
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007